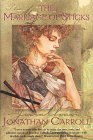Babel’s Lot
2000
A
Wrinkle in Time Madeleine L’Encle A Dell Yearling Books 1962
(五次元世界のぼうけん マデラライン・ランクル あかね書房 1968)
Nurse Matilda goes to Town Christiana Brand, illustrated by Edward Ardizzone E.P. Dutton (USA) 1968
Song
for the Basilisk
Patricia Mckillip Ace books 1999 Hardcover
1998
1999
Winter Rose
Patricia McKillip Ace books 1997
Hardcover 1996
In Pursuit of the Proper Sinner. Elizabeth George 1999
Bellwether. Connie Willis 1996 Bantam Spectra Book New!
The Marriage of Sticks. Jonathan Carroll 1999 Tor Books
To say nothing of the Dog. Connie Willis 1998
1998
As she climbs across the table Jonathan Lethem, 1997
Vivia. Tannith Lee (UK version) 1995
Reigning Cats and Dogs. Tannith Lee
Headline, 1995 (Paperback 1996) in the UK
Life, the Universe and Everything
Douglas Adams
The Case Has Altered : A Richard Jury Mystery
Martha Grimes 1997
Weighed in the Balance Anne Perry 1997
The Echo Minette Walters 1998
The Hundred Secret Senses. Amy Tan
Deception on His Mind Elizabeth George
1998
A Widow for One Year John Irving 1998
Kissing the Beehive. Jonathan Carroll
Before 1997
The Panic Hand. Jonathan Carroll
Lost Souls. Poppy Brite
Drawing Blood. Poppy Brite
Song for the Basilisk by Patricia Mckillip
お話
ベリロンの都の夜、トルマリン館で、旧家の当主と一族が惨殺され、一人生き延びた子供は、魔物が住むとさえ噂される北の果て、ルリー島へと落ち延びる。そこで吟遊詩人の学校に預けられたルーク(鴉)・カドラリスは優れた音楽家となるが、吟遊詩人として立つことを拒否し、子供を得て静かな37年をすごす。だが壮年になったカドラリスは自らの謎に追いつめられ「奥地」に出かけ、死者たちによって、最初の吟遊詩人から伝わる楽器と音楽の真の力を見出す。ルリーの学校が滅ぼされた後、カドラリスは運命に曳かれて、ベリロンの都に戻ってくる。
一方ベリロンの都では、音楽の優れたパトロンだが残虐な支配者でもあるベリロン公の元で、都の音楽学校の楽師匠たちが、かつてはトルマリン家に保護された学校を守るために、健闘していた。年若い楽師のジュリアはベリオン公、ペリオール家のアリオーソの誕生祭の歌劇の準備を引き受ける。
アリオーソは、37年前の惨殺の主であり、強大な魔力の主であり、ペリオール家の守護獣でもある、バシリスク(この世界では普通に生息している)そのものに比される存在。しかし、公の力を受け継けついだ、冷ややかで鋭い公女ルナこそがカドラリスに正面から対することになる。(この設定が魅力的)一方カドラリスは、素朴な農夫の外見を持つ中年男で、にえきらないタイプ。だがカドラリスもまた、彼の真の名であるグリフィンとして、また父の名であり借りの名である大鴉の力を備え、荒地で得た破壊的な音楽の知識を抱いている。
ペリオール宮に、音楽学校の楽譜司書として潜入したカドラリス。トルマリン家の傍系の若者たちのクーデターの陰謀、カドラリスの息子のホリスの思惑、カドラリスに恋する公女ダミエットの行動が、ジュリアたちがたちがアリオーソの誕生祭のために準備する歌劇と同時進行する。歌劇は、まさに追われた公子が都に戻って、ペリオール家の娘と恋に落ちるという状況そのままを写していた。
「死んでしまった子供」の視点から、荒涼とした辺境への逃亡と音楽の探求がはじまる物語の皮切りは鮮烈。自分がちょっと傾いてる読み手だと思う人は感じるものがあるのでは。カドラリス、音楽家のジュリア、令嬢ルナの多視点がめまぐるしく変わるが、ストーリそのものはすっきり進む。涼やかで繊細だが、鋭い暗喩を多用した謎めいた美文は魅惑的である。浅羽氏か井辻氏に是非訳してもらいたいものだ。たいていの登場人物が、配慮がなくて自分をあまり大切にしていないことも、マキリップ独特の浮遊感とあいまって神話めいた雰囲気に貢献している。
最後はえっ、これで終わり!というような結末。こう書いても不親切じゃないと思うのは、作者のねらいが驚かせるというレベルにないことがあきらかだから。それなりにカタルシスはあるし、あるキイパースンが真意の知れないキャラクターのままであることとか、対立が結構簡単に解消されることも、それはそれでいいと思う。しかしすっきりしない。
ファンタジーでの「謎」の扱い方は、ミステリともSFとも違う。だからさまざまな謎がきちっと回収される必要はないのだが、やはり竪琴と農夫の風琴の役割の謎、ルリーの音楽学校、辺境のなりたちの謎などもうすこし追求してほしい。ミステリに慣れた身としては、37年前の惨殺事件に、たとえば子供の死体の正体とかに仕掛けがあったら面白くなるのに、と期待してたのだが残念。乱舞するバシリスクやグリフォンが、人の操る力の象徴程度にしか扱われないのも惜しい気がする。ただしこれは私の英語力のせいで、与えられている答えを見落としていたり誤解している可能性が大なので、和訳だったらもっとすっきりするだろう。
『イルスの竪琴』が好きな人にお薦め。わたしは『サイベル』より『イルス』派なので、あの疾走感と浮遊感を堪能。
読み手(わたし)のほうの問題として、タニス・リーみたいに構文や語彙が難しいというのじゃないが、とにかく比喩と事実の区別がつけにくかった。細かい謎めいた表現を回収しないで次々に進んでいく。難しい単語はとばせばすむ(<悪い例。いい子は辞書をひきましょうね)がこういうわかり難さのほうが確かに読書力・言語能力を選ぶ。翻訳で読めばなんということもないのだろうが。
名前もどう発音するか難しいなあ。いつも正しい発音をしているというのではなく、テキトーに読んでるのだが、テキトーに見当つけにくいつづりというのがある。それでも緊張感があって面白いし、ひきこまれるので最後まで読むのには問題ない。
Winter Rose Patricia McKillip Ace books 1997 Hardcover 1996
Winter Rose

魅力的だが孤独で控え目なコルベットと、リン家の子孫にかけられたという呪いが気になるローズは、村の老人たちにリン家の惨劇について尋ねてまわる。孤独な子供だったティールは、父の死体を残し、冬の雪に足跡を残さず消失した。彼はどこに消えたのか?ナイアルが死の息で、ティールと子孫にかけた呪いとはなにか?コルベットはどこから、なぜ暗い噂のある村に帰り、かつての屋形を再興しようとしているのか?
森の妖魔の不思議な力を感じるロイスは、森の闇と冬がコルベットを捕らえようとしていること、そして彼が助けを求めていることを知る。しかしコルベットはロイスでなく、優しい姉娘ローレルと恋に落ちようとしていた。
前半の緊張感にくらべて、後半の決着の付け方は、ロイス自身の素性と感応力の秘密も含めて、やや物足りない。舞台は村と森の間で終始し、登場人物も少ない。無駄のない構成で最後までさっと読み通せる。もう一歩いったら、魅力的な幻想ミステリ(魔法と妖精の存在する世界で、呪われた家族の過去を探る)になり得ただろうが、もともと作者にその気があったとも思えない。後半、謎よりも、姉を救うために捕われの青年を助け出そうとする少女の葛藤が中心になる。
Bellwether. Connie Willis 1996 Bantam Spectra Book
Bellwether
途中まで、このタイトルを Belle weather「いい天気」だと思いこんでいた。恥をかくまえに気が付いてよかった。wether ? weatherの異綴語かジョークか?と思って辞書を引いたら、Bellwether = 鈴付き羊(先導の羊)、先導者、とある。無知は恐い。いらない恥をかくところでした。最初の数ページを読めば、この本の主モチーフが、「流行」= fad であるとすぐ分かるのに。でも、コニー・ウィリスって痛い批評や嗜虐(我が愛しき娘たちよ!)を十分含むにもかかわらず、おとっとり晴れやかな好天気を思わせる作家だよね?(言い訳)問題の、bellwether にあたる羊さんは比喩じゃなく、ちゃんと当人(当羊?当獣?)が後半登場し活躍する。
フェアリーテイル
これは科学者、エンジニア、そしてすべての組織の中で苦闘するプロフェッショナルのためのおとぎ話。
主題が流行なら、副主題は、科学のブレイクスルーはどこから来るのか?
ウィスコンシン州はボールダー、民間の研究所HiTek で、「流行」のひき金は何かを日々研究する社会学者サンドラは、事務方の官僚主義と会議と申請書の山に苦闘する日々。歩く災厄のような事務アシスタントの女の子フリップ (Flipping って書類などをパラパラめくる時に、日常的に使う言葉)は、コピーを取り間違え、重要書類を無くし、雑用を増殖させ、意味不明瞭な言葉とファッションを持ち込む。配達間違いの荷物を届けに生物ラボを尋ねたサンドラは、浮世離れした研究者、ベネット・オレイリーに出会い、フリップと会社の被害者として意気投合する。この辺り、脱力のマネージメントと苦闘するサラリーマンエンジニア漫画 Dilbert のノリである。
ベネットはマカクの群れの行動伝播から、カオスの構造を研究しようと計画していた。
ベネットが、書き込むのに永遠にかかる研究費申請書類の提出期限に遅れ(誰あろうカオスの化身フリップのおかげで)予算なしで追い出されれそうになったとき、サンドラは、羊の群れの行動のトレンドを研究すると称し、彼のカオス理論の研究と自分の研究を共同研究にすることを提案し、友人の羊の群れを研究所に持ち込む。官僚主義サバイバル術の天才である同僚ジーナの、絶対通るプロポーザル生産の妙を見よ!
しかし会社経営陣は、最高レベルの研究グラント、ニーブニッツ賞を狙える研究をさせようと、研究者たちの尻をたたいていた。適当にでっちあげた研究は、会社のめがねにかないすぎてしまった?ひとつのトラブルは次のトラブルを生み、研究所を巻き込む大騒ぎにと発展していく。
なぜ人は、ロマンティク花嫁衣装バービー人形に、ティラミスに、健康茶に、禁煙に狂奔するのか?なぜささやかだが愛すべき個性と嗜好は、大勢に洗い流されてしまうのか。科学は科学者を統計的に管理する事で達成できるのか。コークでべとべとの書類、届かない手紙、誤解と行き違いと失望と、すべての混乱や混沌には意味があるのだろうか?
その答えと、そしてニーブニッツ賞への鍵を握るのは、頑固なベルウェザー=先導の羊と、そして・・・?
超一流のストーリーテリングと細部の巧みさで、堂々と予定調和的な恋の喜劇、プーク、そして「妖精のXXXX」を堂々と書いて楽しませてくれちゃうのがこの人の真骨頂。ストーリーは予測可能だが、魅力は別のところにある。最後にいたって、これがまさしく御伽話だとわかるが、底流のリアルな苦さも軽く忘れられるようなものではない。
リメイク
長編としては「リメイク」の直後の作だが、運が悪いとヒューゴー賞受賞の To Say Nothing of the Dog が先に翻訳されてしまうかもしれない。おそらく、その方がマーケットに会っているだろう。羊さんのほうは、十分に佳作なんだがジャンルSFファンがまとめてターゲットと言うより、巧みな語りや構成力に特に惹かれる小説好きに訴える要素が強い。まあこの二つのグループを分ける意義があるとしたらの話。実際、この作品はSFの範疇にははいらない。重要な科学技術的発見や歴史的変動がすでに起こっていて、それがストーリーに重要な意味を与えているという世界ではないからだ。例えば、近未来ハリウッドのネットワークと電子技術を生かしたリメイク映画というような、明確な題材がない分「ベルウェザー」はSFプロパーのファンにはアピールしにくいと思われる。でも面白いんだよ。
各章冒頭に、過去の歴史の無数の流行りものへのコメントが挿入される。アリス・ブルーから、中世の舞踏熱、禁酒法、催眠術、QC、ホットパンツ、ディケンズの骨董屋等などなど。これはリメイクの映画台本についてのコメントが章冒頭にあって、ストーリーが短い章立てで進んでいくのと似た構成。すっきりした構成の妙で次々に読ませるパワーと、「流行りすたり」という軽やかな主題を鳴らしながら、失われていくものへのせつなさがさらりと提示されるところは、「リメイク」と共通している。
蛇足いろいろ
私は統計学入門レベルの知識でオリジナルな計量分析を捨てた(いや捨てられた)人間ですが、わざとらしい多変量解析その他がパロディであるくらいはわかる。だから科学云々というのはあくまでも物語内リアリティのレベルのことです。念のため。
さて、主筋とは外れるところだが、読書好きのためにぜひ引用しなくちゃという場面あり。
“Why are you throwing out Dickens?” I’d asked Lorraine last year at the library book sale, brandishing a copy of Bleak House at her…
“Nobody checked it out,” she’d said. “If no one checks a book out for a year, it gets taken off the shelves.” …“Obviously nobody read it.”
“And nobody ever will because it won’t be there for them to check out,” I’d said. “Bleak House is a wonderful book.”
“Then this is your chance to buy it,” she’d said.
Well, and this was a trend like any other, and as a sociologist I should note it with interest and try to determine its origins. I didn’t. Instead, I started checking out books. All my favorites, which I’d never checked out because I had copies at home…
(p22)
絶版の嵐に悩む日本の本好きにもよくわかりますね、このセンチメンタリズム。
コニー・ウィリスってキッチュを排除した、過去のフェアリーテイルの光栄を確信犯的に再構築してるんだと思った。世界的にオタクが氾濫した後の時代を、意図的になかったことにしてるんで、スマートで意地悪だし、結構SFに対するステイトメントにもなってたりして、と思うのは日本のSFシーンからの類推でありすぎるか?もちろん旧来の大衆文化批判スノビズムじゃない。ディケンズだって大衆向け感傷主義であることを否定しないで、That’s Entertainment! 的なもの、ノスタルジアに浸る自分自身を笑ってみせる。見せながら二転三転させて読者を取り込む魔術師の手腕こそがすべてなんだと思うんだが。
Vivia Tannith Lee (UK version) 1995
ご存知タニス・リーの甘美で耽美な美少女吸血鬼の遍歴物。まさにリーのヒロインというべき、冷感症的というか情緒不全の美少女ヴィヴィアが、中世風の地方領主の父親の圧制、城の全員が死に絶える疫病、地底に眠る妖魔の王子の抱擁(とその先)、砂漠の都に君臨する魔術王の慮囚、ヴィヴィアの魔性を巡る宮廷の陰謀、放浪の果ての娼婦という華麗で残酷な運命を、冷ややかに受け入れて行く。というより、妖魔の王子との一時の交歓の後、ヴィヴィアは吸血鬼らしき存在になり、変貌を重ねるのだが、この少女あまり自覚がないというか、そんなことどうでもいいらしい。彼女が出あう王侯貴族や魔女たちも酷簿だが、ヴィヴィアのほうも輪をかけて冷淡。最後に、誠実にヴィヴィアを愛する青年に出会うが、吸血鬼の愛は・・・。
「この時より後、我が眠りの内には、永遠にそなたがあろうよ」と告げて妖魔が去るところなんか、きゃーっと嬉しがらせてくれて、個人的にはリー女史ひさびさのヒット。「黄金の魔獣」よりもはるかに本邦のT・リーのファンの好尚に会うと思えるので、なぜこちらがさっさと翻訳されなかったのか不思議。きっと「黄金の魔獣」のアブナイ美青年たちが、女性翻訳者と編集担当者の煩悩を揺さ振ったのでは?それはそれで大変に正しい考え方ではあるけれど、「ヴィヴィア」もちゃんと文庫でださなけりゃだめ。世界は違うが、美学的共通性から、「平らな地球」シリーズファンには、特に必見と思われる。
英国で買ったペーパーバックは、マンチェスター市立ギャラリーの「サッフォー」、有名な、暗い背景に浮かびあがる白い肌の魔性の女の像が、表紙となっていてぴったり。鞄にはいらず処分しちゃったのが惜しまれる。
追加
タニス・リーについてはここに充実した文献情報があり役に立つ。多作だが品切れも多い作家だし、これほど短編を書いているとは知らなかった。
タニス・リーのリスト Daughter of the Night
The Marriage of Sticks, Jonathan Carroll 1999
34歳の有能な稀稿本書店主のミランダ・ロマナックは、どこかで空虚な不安を抱えて日々を過ごしている。出張先で空港に行く途中、車のライトの中に一瞬浮かびあがる、夜の国道の路傍に孤独にたたずむ車椅子の老女に心を揺さぶられるほどに。
田舎の高校同窓会に出席したミランダは、かつてのボーイフレンド、ジェームス・スティルマンが若くして亡くなっていたことを知った。才気のある不良少年ジェームスとの恋を思い、人生から失われてしまった様々な可能性に傷つくミランダ。
ニューヨークに戻った彼女は、奔放な人生を送った老婦人フランセス・ハッチと知り合う。ヨーロッパで長年過ごしたフランセスは、芸術家や富豪たちと愛しあう恋人として、自由に生きて来た。(アナイス・ニンや、先年亡くなったフランス駐在大使、パメラ・ハリマンなどを思わせる?)
フランセス所有の、謎の画家アドコックの絵が機縁となって、画商のヒュー・オークレイに出会う。彼は、美術エージェントのキャリアを始めたばかりだったジェームズの死の事情を知っていた。そしてヒューには美貌の妻と子供が居るにもかかわらず、二人は恋に落ちる。
最初の100ページは、不良少年とのときめく恋の思い出、妻のある魅力的な男との恋愛などが、さらりと詩的に語られる。しかし客観的に見れば平凡な物語の中に、不協和音が徐々に混ざり初めてくる。ときおり現われる死者の姿、ヒューの離婚、謎めいた絵。回想の語り手ミランダの現在の身辺に漂う、悪意と狂気の気配。
このあたりから先は配慮してはありますが、多少のネタバレあり
ヒューとともに、ニューヨーク郊外の街、クレインズ・ヴューにあるフランセス所有の家にミランダは移り住む。ミランダはその家に異様な存在を感知し、これから生まれてくる子供、ジャック・オークレイの幸せな姿を幻視する。だが離婚を控えたヒューと幸せな暮らしがはじまるやさき、悲劇が襲う。
表題の「薪の結婚」は、ヒュー・オークリーがミランダに伝えた習慣。
人生の終わるとき、暖炉には一束の木端れがあるようにしよう。ほんとうに重要な出来事があったとき、手近な一片の木端れに日付と理由を書き付けておく。何年かごとに、本当に重要だった出来事だけよりわけて残す。老いてもう時間がないとわかったとき、すべての薪を燃やすことを自分に課す。(Marriage
って「一揃い」という意味もあるらしいが、ここはやはり一揃いの薪よりは、結婚でしょう。自信はないけれど)
クレインズ・ビューにつぎつぎと死者が立ち現われ、ミランダが幻視する奇妙で美しい光景の意味は?ミランダの持つ力とは何か?前世の、そしてこれまでの人生で犯した「罪」とはなにか?
ミランダとフランセスの過去が絡み合い、前半の人間関係のなかで描写された一つ一つの挿話が恐ろしい別の意味をもって解き明かされて行く。
幻の子供、ジャック・オークレイとは誰なのか?
ミランダが燃やす人生の薪とは?
死者や異界の力を持つ存在がつぎつぎに登場する。しかしこの物語でいちばん怖いのは、what if? あのとき別の選択をしたら、人生はどうなったのだろうという疑いだ。「・・・もし、この恋がそういう恋だったら?あきらめてしまったあとで、人生でこんな想いは二度となかったと後で知ることになったら、どうしたらいいの?」とミランダは問う。人が「選択しなかったら起こったであろうこと」を知ることができたら?
魔法の存在はありきたりの「攻撃」などしない。懐かしく恐ろしい姿をとって立ち現われ問いを突き付けるだけ。しかしこれが怖い。キャロルの恐怖はオーダーメイドである。天上の愛を極上の描写で読者に与え、次の瞬間地獄に落とす。愛するに価する人や芸術、壊れやすいと知りつつ守ろうと努力しているものを奪っていく。
ジャック・オークレーの正体、最後まで持ち越されるミランダの選択の謎、最終的に語り手の現在と過去を自在に操る構成は、手慣れていて独創的。これだけでも十分読む価値がある。
ここから先は批判!いやな人は読まないこと。
ジョナサン・キャロルの新作について書くことは私には難しい。彼が過去に描いた魅惑的な世界と登場人物たち。生の歓喜と傷、森羅万象の美しいもの、人間的なものへの愛。鋭い刃のような恐怖。洞察と機智に溢れた文章。宝石のような引用。同じ世界の延長を待ち望む気持ちと、一方で、新作ごとに、あらゆる想像を超えた綺想を展開する、題材の斬新さへの期待があるからだ。
さて、正直なところ、The Marriage of Sticks は、私にとっては期待を裏切られるという所があった。前作の Kissing the Beehive に比べれば遥かにましとはいえ、かつての鮮やかな手際が、完全に回復してないと思える。だが私の不満はあくまでも、ファンとしての矛盾した要求に基づいているので、かえって目が曇っている可能性はある。他の作家を読んで満足するより、ジョナサン・キャロルを読んでやきもきするほうが幸福であると、私は信じるのだが。
まず登場人物の魅力が今一つである。もともとキャロルの語り手=主人公は映画監督や女優でさえ、むしろ抑制ぎみのキャラクターだが(例外はわがまま野郎の天才建築家ハリー・ラドクリフ)、周囲の脇役、とりわけ主人公の恋人と、彼(彼女)の友人は、心の楽器の弦をすべて鳴り響かせるような生き生きと魅力的な人々が登場するのが常だった。
主人公ミランダも今ひとつ共感しにくいが、しかし、なにより愛人のヒュー・オークレイが、適当な中年男のようにしか見えないのがつらい。最高のときめきと、最悪の恐怖を与える存在、ジェームス・スティルマンもかろうじて役回りに合格したくらいか。友人のゾウイは、ニック・シルヴィアンやフィンキー・リンキーにはおよばす、導き手のヴェナスクにあたるフランセスは、ヴェナスクのような愛敬と魅力に乏しい。前回から登場の、クレインズ・ヴューの警察署長のフラニーも、今一つ不足。
勝手なことをほざいている?でも、キャロリアンワールドにおいて、登場人物に魅惑されないというのは、異常事態なのだ。
冒頭で心をひっつかむような挿話やセリフをたたみかけて、読み手を捕らえる魔術的技術も今ひとつ働いていない。車椅子の老女も、ミランダが口で言うほど迫ってくるだろうか?それとも私がなにか間違えているのだろうか?浅羽莢子訳でなければ楽しめないのか?(でも最近の4つは英語でまず読んだのだけれどなあ。)うーん。泣きたい。
いくつかの画面は、むしろ過去の作品と同工異曲に見えるところがある。テレビの画面に中で、ありえざる映像が見せられるのは、「空に浮かぶ子供」のヴィデオテープを思わせるし、前世の成り立ちについても「炎の眠り」と似ている部分がある。つぎつぎに死者が立ち現われて語りかける様や、異界の代理人としての催眠術師シュムダは「天使の牙から」を思わせる。息をのむような奇想をこれまで見せられて来た側としては、どうしても、今ひとつ、という気にさせられる。
第三に、主題らしきもの位置に混乱させられる。かつては「自分自身を知れ」とか「人は死を超えられない」という説教をたれても、寓話的な物語の意匠と不可分で、突出していなかった。今回そのへんに無理がある。これはミランダの「罪」が、いまひとつ読者に説得力がないことにあるのではないだろうか。ただ主題の座りのよさは人によってボーダーラインが違う。ワタシは「空に浮かぶ子供」の最後も好きだが、とってつけたようだと思う人もいたらしいので、ぜひ自分で読んで判定して欲しい。
日本人にとって難しいところは、日本の小説では、前世因縁譚はひとつのクリシェに達している。ちょっとでも因縁話的に見えたら、読者を醒めさせてしまう。欧米の読者ではそうでもないかもしれない。今までのところ、キャロルはヨーロッパ的世界の中で、キリスト教的ではまったくない、寓話的ダークファンタジーを築いてきた。それが、だんだん表層的なほうに近づいていると思うのは、僻目か?
キャロルは「沈黙の後」以降、前の連作の世界からいったん離れて、新しい舞台と方法を摸索しているように見える。「天使の牙から」では、また以前のキャラクターと世界を使いながら、新機軸をうちだしているけれど「Kissing the Beehive は、幻想的モチーフを抑制した普通小説に近いものだ。しかし強烈に魅力的で、根源的恐怖を感じさせる人物が登場し、それだけでも力があった。クレインズ・ヴューに腰を据えると決めたようなので、今後に期待するとしますか。
To say nothing of the Dog, Connie Willis 1998
おなじみの21世紀のオックスフォード大学史学部、ダンワージー教授の下の歴史学者たちが活躍する時間旅行SFミステリ。でもメインはラブコメ。
21世紀の歴史学者ネッド・ヘンリーは、ナチスの空襲で破壊された、旧コヴェントリー大聖堂をオックスフォードに復元しようという女傑レディ・シャラプネルに貸し出されてこき使われる日々。「神は細部に宿る」との信念のもと、史学部と時間局の人員を根こそぎにして復興事業の資料収集を指揮するレディには、ダンワージー教授さえ頭を抱える。
聖堂から空襲直前に姿を消した「司教のバード・スタンプ」なる飾り台の行方を探すために、時間旅行を繰り返してタイムトラベル・ハイになってしまったヘンリーを、教授は休養のためにヴィクトリア朝に送り込んだ。
ところがその頃、時間旅行用「ネット」によるヴィクトリア朝への旅行には前代未聞のトラブルが生じていた。ネットは帰還時に、旅行者が元々所持品以外のいかなる物質も運ぶことができないシステムのはずだった。だが、これもレディ・シャラプネルの命を受け、レディの先祖の元に送り込まれていたヴェリティ・キンドルが「あるもの」を持ち帰ってしまった。
時空連続体は、最終的に歴史を修正して軌道にもどすため、細かい変化を引き起こすだろう。だが、どんな変化が起こるかはヘンリーたちにさえわからない。いちど移動された「それ」を、元の時空に戻すのが正しいのだろうか?それともそうしたら再び、歴史に介入してしまうのか?
ろくな指示もなく1888年に飛び込んで、頭を抱えるヘンリーは、オックスフォード大学生の青年紳士テレンスに巻き込まれて、古きよきテムズの川下りを始める。お供はブルドックのシリル。議論に夢中になってテムズに落とされたペドウィック教授を救助し、テムズの河旅は続く。
テレンス青年は、舌足らずで可愛いでもはっきりいっておつむのやや軽い令嬢トッシーに恋は盲目状態。実はトッシーこそが、レディ・シャラプネルの先祖であり、彼女は、この数日中に未来の夫と恋に陥り、コヴェントリー大聖堂で「ビショップのバードスタンプ」(というのは鉄製の花瓶などを置く置きもの)にかかわる重大な経験をし、それを日記に書き残す予定だった。しかし、トッシーの従姉妹として潜入していたヴェリティの行為と、ヘンリーの登場がひきがねになって、トッシーは本来の相手でないテレンスとくっついてしまう。彼女の恋の行く末が、周り回って二次大戦時の英国の運命にまでかかわるかもしれない。
物語の鍵を握るのは、トッシーの愛猫、したたかで愛らしく神出鬼没のプリンセス・アルジュマンド。そのほか、七面六臂の活躍をする「賢い執事」ベイン。交霊術に夢中のトッシーの母など英国ホームコメディのキャラクターが満載。時間旅行の合間には、なんとダンワージー教授の青年時代まで出て来る。教授のファンは必見!
ヘンリーたちが過去に出会う楽しく愛すべき人々は、自分達の未来に何が待っているか知らない。絢爛たる聖堂の伽藍も、人の想いも歴史の闇に消えて行く。そこからなにかを救うことができるのか?最後に歴史から救いだされるものは何だろう?約束しよう。素敵な贈りものが待っている、と。
この小説、高名なヴィクトリア時代の爆笑紀行小説、 ジェローム・K・ジェロームの「ボートの三人男(犬は勘定にいれません)」
Three men in a Boat: To say nothing of
the Dog のパスティーシュになっている。原本は、三人の紳士と一匹の犬がテムズ川のボート旅行に出かけるという筋のどたばた喜劇とレトリカルな美文調の旅行案内。主人公が原作のファンで、その上ジェロームと仲間、それに好戦的なモンモランシー(我が尊敬すべきフォックステリア)にテムズ川上で出会うという作者の遊びもある。
おっとりのんびりとした定石のロマンスが展開する一方、次から次へと謎が飛びだす。頻発している時間旅行の誤差の謎は?本来トッシーが恋に落ちるべき人物は誰?空襲直前の聖堂から密室状況(?)で消え失せた飾り台の行方は?キンドルはミステリファンで、しょっちゅうクリスティとセイヤーズを引用している。
マニアが熱狂するジャンル作家ではなく、メロドラマ風のストーリーテリングによって推理小説をエンタテインメントとして確立した、セイヤーズとクリスティに、コニー・ウィリスがオマージュを捧げているのは興味深い。ウィリスは、先行する伝統で鍛えられたストーリー・テリングのスタイル(成長小説、宗教小説、ゴシックロマンスに、スラップスティック、そして今度はミステリ)を常に意識している作家だ。鋭い批評精神と不可分のSF的小道具が、かなり保守的な安定した語りの中に組み込まれたとき、この人らしい威力を発揮する。ウィリスは思想の人でなく、批評精神の作家。時にそこが見過ごされているような気がする。最初にフェミニズムとくっつけて語られることが多かったせいだろうか。(いや、あたしはフェミニズムも自己完結した思想じゃなく、批評精神のことだと思うのだけれど)
追加(30/01/2001) 『蒲生邸事件』(宮部みゆき 1997)が面白かった人にも本書は興味深いのではないかと思う。


 Vivia
Vivia