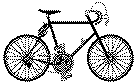変化を必要とする三人の男 欺瞞は悪い結果を生 むという挿話 ジョージの道徳的怯惰 老水夫 行及びに未熟な船乗り 陸風時に航海することの危険 海風時に航海する不可能さ エセルバーサの議論好 きに ついて 川の湿気 ハリスは自転車旅行を提 案する ジョージは風が心配 ハリスが黒森 を示唆する ジョージは登ぼり坂が心配 丘を昇るについてハリスが採用した計画 ハリス夫人による中断
「ぼくたちが求めているのは」ハリスが言った。「変化だ」
そのときドアが開いて、ハリス夫人が首を覗かせた。
クラレンスが居るのだから、家に帰るのが遅くなりすぎないようにしなければ、と
エセルバーサの伝言を伝えてくれた。ぼくの意見では、エセルバーサは子供たちについ
て必要以上に神経質すぎる。
実際のところ、クラレンスにはなにひとつ問題はないのだ。
ただ単に、クラレンスは伯母さんに連れられて午前中からでか
けていたというだけのことなのだ。奴がものほしげに菓子屋のウィンドウを見ている
と、
伯母さんときたら店に連れてはいって、クラレンスが腹いっぱいになって、もちろん
礼儀正しく、だが断固として、それ以上一口も食べられないよと拒否するまでは
クリームパンと「花嫁のつきそい」メイドオブオナーケーキを好きなだ
け食べさせてやる。
当然、昼食には、プディングをひとすくい欲しがるだけ。
それでエセルバーサは、あの子が何かで体調が悪いのだと思い込んでしまう。
ハリス夫人が、はやく二階に来ないと後で後悔しますよ、と呼んだ。
ミュリエルが「アリスの不思議な国」の気違いお茶会の巻を一人芝居で演じるのを見逃
してしまうと
付け加えて。
ミュリエルはハリスの二番目の子で、8歳になる。活発で頭のいい子供だ。でも、ぼく
の個人的な意見としちゃ、ミュリエルは、なにかもっとおとなしい話を演じたほうがい
いんじゃないかと思う。
いそいで煙草を一服したら後からすぐ行く、とぼくらは答えた。ぼくたちが行くま
では、ミュリエルにはじめさせないでください、とも頼んだ。ハリス夫人はできるかぎ
り
は待たせておきますけれど、と請け合って出ていった。
ドアが閉まったとたん、ハリスは中断された言葉を続けた。
「わかっているだろう?」彼は言った。「完全な気分転換だよ」
問題は、どうやってそいつを手に入れるか?だ。
ジョージが、「仕事」はどうだい、と尋ねた。
いかにもジョージのような男が思い付きそうな提案である。独り者は、結婚している女
というものが、つき進んで来る蒸気機関車から、線路をおりてよけることも知らないほ
ど
無知だと考えているのだ。
ぼくの知り合いの若い技術者のことを思い出す。その男も「仕事で」ウィーンに出か
けることを思い立った。彼の妻は、いったい何の仕事だか知りたがった。男は、自分の
任務はオーストリアの首都近郊の鉱山を視察して、報告書をつくることだと教えた。
そこで奥方は同行しようと考えた。つまり彼女はそういうタイプの女性だったというこ
とだ。
男は妻になんとかあきらめさせようと説得した。鉱山というのは美しい女性が行く
ような場所ではないと言って。
彼女も、まさしくそう思っていたところだった、と答えた。ついては、
シャフトの下まで夫の供をする気はない。たぶん、夫を朝見送ってから、
夕刻帰ってくるまでの間、自分一人でなんとか楽しみをみつけられる。ウィーンの店を
見て歩いて、もしかしたら欲しいかもしれないものをいくつか買いものしていればいい
だろう。
そもそも自分からこの話をはじめてしまったために、その男はこいつをきりぬけること
ができなかった。
結局のところ、夏の10日の間、ひねもす彼はウィーン近郊の鉱山を見て歩く
はめになった。そして夜には鉱山に関する報告書を書き、奥方がそれを奴のために会社
へ郵便で送ってくれた。むろん会社はそんなもの必要としていなかったのだが。
ぼくは、うちのエセルバーサとハリス夫人が、そのようなたぐいの細君に属している などという嘆かわしい意見を持ってはいない。だが、それはそうとして「仕事のため」 というせりふは濫用しないほうがいいだろう。もしもの時のためにとっておくのがいい と思われる。
「だめだよ」ぼくは言った。
「こういうことは、率直で男らしくあるべきなんだ」
「ぼくはね。エセルバーサに言うつもりだ。男というのは、自分が常に享受している
幸福に感謝することができない、という結論に達した、とね。だから、ぼくが感謝
して当然の、君達とともにあるという幸福を、ぼく自身がはっきりと肝に命じるために
は、妻と子供たちから、少なくとも三週間は無理矢理引き離されなければならない。絶
対そう言ってやるつもりだ」
僕はそう続けて、それからハリスの顔を見た。
「それでさ。君こそが、ぼくにこの崇高な義務を示唆してくれたんだ。
だからみんな君のおかげだと……」
ハリスは、あわててと呼んでもいいくらいの様子で、グラスを置いた。
「なあ君?よかったらだな」彼はさえぎった。
「そんな必要はないぜ。奥方はうちのやつに喋るだろうし……うん。
ぼくは自分にふさわしくない手柄をひとりじめにするのは、嬉しくないね」
「でも君の手柄なんだよ」ぼくは主張した。
「もともと君の提案だったんだぜ」
「そもそものアイデアは君が提供してくれたものだ」ハリスはふたたび遮った。
「男がすすんで型にはまるのは間違いだ。そしてびっちりと息のつまる家庭性というも
のは、
頭脳を飽和させると言ったのは、確かに君だよ。わかっているくせに」
「一般論を言ってたんだ」ぼくは説明してやった。
「そいつがまさにガンときたんだ」とハリス。
「ぼくはその言葉をクララに繰り返してやろうと考えていた。
クララは君の良識を高く評価しているからね。ぼくは確信があるんだが……」
「危険をおかすのはよくない」ぼくは遮って発言権を取り戻した。
「これはかなり微妙な事柄だ。でもちょうどいい方法がある。
ぼくたち二人とも、これはジョージのアイデアだと言おうよ」
時々気がついて腹立たしくなることだが、ジョージという男には、人を助けようという 親切心がまったく欠如している。ジョージの奴は、二人の古くからの友人を窮地から助 けだす機会があったら大喜びにきまってると、誰でも思うだろう。だが喜ぶかわりに、 ジョージときたら不賛成を表明した。
「そんなことを言ってみろ」ジョージは言った。「奥方たちに、ぼくのそもそも
の計画は、みんなでパーティをすることだった、と言うぞ。子供たちもほかの家族も一
緒のね」
「だいたいぼくの心つもりでは、うちの伯母さんも招待して、ぼくが知っている、ノル
マンディ
の海岸の素敵な古城(シャトー)を借りるつもりだったんだからな。あ
そこの気候は繊細な子供達にぴったりだし、牛乳ときたら、あんなのは英国では絶対に
手に入らないんだぜ。それからぼくは、きみたちが僕の提案を覆した、と付け加えてや
る。男たちは男だけですごしたほうがずっと楽しめる、と君ら二人が言ったとね」
ジョージのような男に対して、親切心などというものはなんの意味も持たない。
きぜんとした態度で対応しなければならないのだ。
「君がそのつもりなら」ハリスが言った。
「いっておくけれど、ぼくはその提案を受け入れるからな。その古城とやらを借りよ
う。君は伯母君を連れて来るーーそうなるようにぼくが気をつけておこうーーたっぷり
一ヶ月だ。なに、子供たちはみんな君の事を気に入っている。Jとぼくは付き合わない
よ」
「君はエドガーに釣りを教えてやると約束してたね。そういえば君は野生の獣ごっこも
しなければならないぞ。先週の日曜日以来、ディックとミュリエルときたら君の河馬
(かば)のことばっかり話してるんだ。みんなで森にピクニックに出かけてーーなに連
れはほんの11人だけだよーー夜には音楽と朗読のゆうべということにしよう。
たぶん君も知ってるだろうけれど、ミュリエルはもう六つも朗読のレパートリーを持っ
てるんだ。ほかの子もみんな覚えがはやい」
ジョージは降参したーーやつには真の勇気などないのだーーしかし潔くひきさがったわ けではない。ジョージにいわせれば、もしぼくたちがそういう汚ない罠に訴えるほど、 陰険で卑怯で虚偽を好むたちの人間ならば、彼だって従う以外にないじゃないかという ことだ。そしてぼくがクラレットを、一瓶ぜんぶひとりで飲んでしまうつもりでないな ら、一杯いただけないでしょうかね、と言った。そのうえ非論理的にも、ぼくたちがな にを言おうとかまわないさ、と付け加えた。エセルバーサとハリス夫人は良識のある婦 人たちだから、この提案が彼から持ちだされたなんて馬鹿なこと を、一瞬だって信じないだろうさ、と。
かくして些細な点の決着がつき、そこで問題は「どんな気分転換?」に戻った。
ハリスはいつもどおり、海を薦めた。
彼によれば、今ちょうど、まさにこれしかない!というヨットに心あたりがある。
ぼくたちが自分で操縦できるようなやつだ。
仕事を怠ける新米水夫の一群がうろつきまわることもない。そういう水夫連中は費用の
上乗せだし、ロマンを葬り去ってしまう。ひとりだけ使い走りの小僧がいれば、あとは
ハリスが自分で操縦しようと言うのだ。
ぼくたちはそのヨットのことを知っていて、ハリスにそう言ってやった。
以前ハリスと一緒にそいつに乗ったことがあるのだ。
船底の垢と藻が、ほかのありとあらゆる臭いを押し退けて、におっている。
常識内で思い当たるどんな海の空気も、あの臭いを出し抜くことはできな
い。臭いの件に関するかぎり、一週間をライムハウス(イーストエンドの中国人街)
ホールで過ごしているようなものだ。雨が降ってもよける場所はない。サルーンは10
フィートX4フィートの広さで、その半分はストーブに占領されていて、ストーブは火
をつけようとするとばらばらに解体してしまう。甲板で湯浴みをしなければならない
し、バスタブから出た途端に風がタオルを吹き飛ばしていく。ハリスと手伝いの子が面
白いところーー帆をあげたり巻き取ったり、船を進めたり、傾かせたりというところ
ーーを全部やってしまい、ジョージとぼくにはじゃが芋の皮剥きと洗濯しか残してくれ
ない。
「まあいいさ。それなら」ハリスは言った「ちゃんとした帆船を借りよう。船乗りと一
緒に。全部をまともなやり方でやろうぜ」
これにもぼくは反対した。ぼくは船乗りというものも知っている。船乗りという連中の
航海の概念とは、彼が「沖合」と呼ぶあたりに、停まってゆっくりすることだ。そ
こにいれば細君と家族にすぐ連絡ができて、むろん気に入りの酒場パブ
も忘れてはいけない。
何年も前のこと、ぼくがまだ若く未熟だったころ、自分で小型船を雇ったことがあ る。三つの条件が合わさって、ぼくをこの愚行に走らせた。予想外の収入があったこ と。エセルバーサが海の空気への憧れを主張したこと。まさにその翌朝、偶然クラブで 「スポーツマン」紙を手に取ったところ、次のような広告に出くわしたのだ。
ヨットマンへ告ぐ いちどきりのチャンス 「 荒くれ」号;28トン、ヨール(小型帆船 所有者、突然の出張の ため、素晴らしくスマートな「海のグレイハウンド」を短期長期お好きなだけ貸し出し たし 船室二つにサルーン。ヴォッヘンコフによるピアノ室。新し い炊事ボイラー。 条件;一週間10ギニー バートウィー協会、バッカロウベリ3A番地に申し込まれたし。
これはまるでぼくたちの祈りへの答えのように思われた。興味があったのは「新しい 炊事ボイラー」ではない。洗濯物なんかは後回しにすればいい。それはぼくの考えだ が。しかし「ヴォフェンコフによるピアノ室」はとても魅惑的だった。ぼくはエセル バーサが夕べにピアノを奏でているところを思い描いた。なにか合唱つきの曲を。乗組 員もちょっとの練習で一緒に歌うことができるだろう。歌とともに、ぼくたちの動く家 は「グレイハウンドのように」銀の波間を滑ってゆく。
ぼくは馬車を拾って、バッカロウベリ3A番地に直行した。パートウィー氏は 気取らないようすの紳士で、ぜんぜんみせびらかしたところのない様子の事務所を四階 に構えていた。氏は、「荒くれ」号が順風で疾走しているところを描いた水彩画を見せ てくれた。
甲板は大洋にたいして95度の角度を保っている。その絵では人間は一人も甲板に描か れていなかった。推測するに、みんな滑り落ちてしまったのだろう。実際、どうやって 誰かがしがみついていられたのか、ぼくには理解できなかった。釘づけにされていな かったならばだが。ぼくはこの欠点を代理人に指摘した。しかし彼が説明するには、そ の絵は、回航競争だかなんだかの、メドウェイ挑戦杯において「荒くれ」号が勝利した 有名な瞬間を描写しているということだった。パートウィ氏はぼくがそのような有名な 大会についてすべてを承知に決まっているという態度だったので、ぼくは質問する気に なれなかった。
絵の縁ぎりぎりの二つの点は、ぼくはてっきり蛾だと思いこんでいたのだが、この高名 なレースでの第二位と第三位の勝者を表わしているらしかった。グレイブサンド埠頭に 繋留された船の写真は、それほど印象的ではなかったが、かわりにもっと安定した印象 を与えていた。質問への答えが全部満足の行くものだったので、ぼくは二週間その船を 借りることにした。パートウィー氏によれば、ぼくがこの船を二週間と頼んだのは運が よかったーーぼくは後で彼につよく賛成することになるーーなぜならちょうどその期間 ならば、次の貸し出しまでの間に滑り込むことができたから、ということだった。もし ぼくが三週間必要としていたら、ぼくの申し出を断わらなければならなかっただろう。
そんなぐあいに貸し出しの手続きが終わったところで、パートウィー氏はぼくに、 船長に心あたりはあるか聞いた。なかったのはもう一つの幸運だったーーどうもぼくに は幸運がついてまわってるらしいーーなぜならパートウィー氏によれば、現在その役を あずかっているゴイルズ氏に、そのまま頼むこと以上の幸運は考えられないからだ。ゴ イルズ氏というのは、海のことを男が自分の妻について知っているのと同じぐらいよく 知っていて、ただの一つの命も失ったことがない、傑出した船乗りだとパートウィー氏 はぼくに請け合った。
その日はまだ早かった。船はハートウィッチに繋留されている。ぼくはリヴァ プール街から10時45分の列車に乗って、1時前にはゴイルズ氏と、甲板で話してい た。彼はがっちりした男で、いわば父親的な雰囲気の人物だった。ぼくは自分の、オラ ンダ沖の島々に行って、それからノルウェイにちょっと寄ると言う計画を説明した。船 長は「アイ、アイ、サー」と答え、この旅にとても興味があるように思われた。自分も きっと楽しめるだろう、と言う。話が進んで、積み込む糧食のことになると彼の熱意は ますます盛り上がった。ゴイルズ氏が示した食物の量は、正直言って、ぼくを驚かせ た。
もしぼくたちが海賊ドレイクとカリブ海の海賊の時代に生きていたとしたなら、ぼくは
ゴイルズ氏がなにか違法な活動をたくらんでいると戦慄したにちがいない。
しかし彼は独特の父親めいた態度で笑ってみせて、ちっともいきすぎなんかではないこ
とを教えてくれた。
残り物は乗組員が分かちあって、家にもちかえる。どうもこれは習慣らしかっ
た。ぼくが乗組員たちの冬中の食糧を提供しているような気がしたが、けちけちしてい
ると思われたくなかったので、それ以上言わなかった。必要とされる酒類の量にも驚い
た。ぼくは自分たちのために要ると思われるものを注文した。そこでゴイルズ氏は、乗
組員のことも考えようと主張した。彼のために言っておかなかればならないが、ゴイル
ズ氏はたいへん部下思いの男だった。
「ぼくたちはどんちゃん騒ぎをしたいわけじゃないんですよ。ゴイルズさん」
「どんちゃん騒ぎ!」ゴイルズ氏は答えた。「まさか。連中がちょいとお茶のなか
に落とす分だけでさ」
彼のモットーは、「優秀な人材を雇い、優遇しろ」だと説明した。
「そうすりゃ部下はあんたのためによく働きまさ」とゴイルズ氏。「そして次の
時も連中はやってくる」
ぼくの個人的な意見としては、まったくもって連中に再びやってきてほしくなかっ
た。はじめて会う前から、彼らの事を嫌いになりかけていた。連中は、貪欲で大ぐらい
の乗組員だと考えた。しかしゴイルズ氏はじつに陽気できっぱりした態度だったし、ぼ
くはあまりにも経験がなかったので、ここでも再びゴイルズ氏の好きにさせてしまっ
た。彼は再び、この面についても、何一つが無駄にならないように自分が気をつけると
請け合った。
加えてぼくは、船長に乗組員を雇い入れるのをまかせた。彼がいうのは、全部自分に まかせておけば、ぼくのためにみんな片付けてくれるということだった。もし彼が糧食 と酒を片付けることをほのめかしているのだったら、ちょっと無理な見込みなんじゃな いか、とぼくは思った。だがたぶん、彼は船の航海のことを言っていたのかもしれな い。
帰り道にぼくは行きつけの仕立て屋に寄って、ヨット服を白い帽子を一緒に注 文した。仕立屋は、大急ぎで仕立てて間に合わせると約束してくれた。それから、家に 帰ってぼくはエセルバーサに、ぼくがしたことを告げた。彼女は大喜びだったが、ひと つだけ気に病んだのは「仕立屋は、彼女のヨット服を間に合って仕上げられるかしら」 ということだった。まったく女というものらしい考え方だ。
ぼくたちはしばらく前に新婚旅行に行ったところだったが、短く切り上げ なければならなかった。だからぼくたちは、このヨット旅行に誰も招待しないことにし た。ぼくたちだけに船旅をとっておくことにしたのだ。まったくそう決めたことを神に 感謝しなければならない。月曜日に、ぼくたちは服を詰めて出かけた。何をエセルバー サが着ていたか忘れてしまったが、それがなんであれ、とても魅力的だった。ぼく自身 の衣装は、紺色に白の縫い取りの縁取りがしてあるもので、今思っても、 なかなか気が利いていた。
ゴイルズ氏は甲板でぼくたちを出迎え、昼食の用意ができていると告げた。氏が、か なり腕ききの料理人を確保したことは、認めなければならない。他の乗組員の能力に関 するかぎり、ぼくに判断する機会はなかった。しかし、休息しているところを見る限り では、彼らはなかなか陽気な連中らしかったと言うことができる。
ぼくの心づもりでは、乗組員が晩餐を終えたらすぐさま、錨をあげるだろうというこ とだった。その間、ぼくは煙草に火をつけ、エセルバーサと寄り添って、舷側によりか かり、父なる国の白亜の崖がほのかに水平線に消えていくさまを眺めていよう。エセル バーサとぼくに関するかぎり、その予定表の自分達の役割をちゃんとはたした。甲板に 二人きりで待っていたのだ。
「どうも時間がかかるみたいね」エセルバーサが言った。
「もしも、14日の間に連中が船に積んである食糧の半分を食べてしまうなら、食事の
たびにずいぶん時間が要るだろうさ。せかしたりしないほうがいいな。さもないと、四
分の一も片付けられないだろう」
「眠ってしまったんじゃないのかしら?」しばらくして、エセルバーサは言った。「も
うすぐお茶の時間だわ」
たしかに彼らはとても静かだった。ぼくは船首へ行って、ゴイルズ船長を梯子の
下でつかまえた。ぼくが三回呼び止めると、やっと彼はゆっくり上がってきた。船長
は、ぼくが前に見たときよりも、太っていて年を取ったように見えた。口に火のついて
ない煙草をくわえている。
「いつ準備ができるのかな?ゴイルズ船長」ぼくは言った。「出発だよ」ゴイルズ船長
は、口から煙草をはずした。
「今日はだめでさ」と答えた。「旦那のお許し次第ですがね」
「どうして?いったい今日でなにがまずいんだい?」ぼくは言った。船乗りは迷
信深い連中だということを知っていた。思うに、月曜日は不運な日だとされているの
だろう。
「日が悪いんじゃねえですけどね」ゴイルズは答えた。「風向きのことを考えてたん
で。どうもたいして変わんねえみたいでさ」
「しかし、風が変わらなきゃならないのかい?」ぼくは尋ねた。「ぼくにはまさし
くdead最高の風向きに思えるけれど。ちょうど追い風だ」
「アイ、アイ、サー。まさしくdeadっちゅう、その言葉です
わ。俺たちみんな、くたばっちまう。神様のお助けがなしに、俺たちみんながそん中に
放りだされた日にはな。わかんねえですか、だんな」船長は、ぼくの驚いた顔を見て、
説明してくれた。「こいつは俺たちが、陸風と呼んでるやつで、おわかりでしょうが、
まさに陸地からぶうぶう吹いているんです」
説明を聞くにつれ、この男の言ってるとおりだとわかった。風は陸から吹いている。
「夜のうちに風は変わるかもしんねえ」さっきより希望をこめて、ゴイルズ船長は言っ
た。「いずれにせよ、こいつはそう強くねえ。船はうまく進みますよ」ゴイルズ船長
は、煙草に戻った。ぼくは船尾に戻って、エセルバーサに遅れの理由を説明した。エセ
ルバーサは、乗船したときほど陽気でないらしく、いったい「なぜ」我々が、風が陸か
ら吹いているとき、出立できないのかを知りたがった。
「もし風が陸側から吹かないとしたら」とエセルバーサ「海から陸に向かって吹くこと
になるじゃないの。そうしたら、船は岸に押し戻されてしまうわ。まさしく今のこの風
が、私たちに必要な風のような気がするのに」ぼくは言った。「そう思うことこそが経
験の浅い証拠なのさ。ねえ君。これは一見正しい風のような「気がする。」でも違うの
さ。これは陸風と呼ばれていて、陸風というのは常にとても危険なんだ」
エセルバーサは、「なぜ」陸風が危険なのか知りたがった。
彼女の
議論好きな性質にぼくは多少うんざりした。たぶん、ぼくはちょっと不機嫌だったのだ
ろう。停泊した小型船の単調な揺れというのは、はつらつとした精神をも落ち込ませる
ものなのだ。
「君に説明してあげることはできない」と、ぼくは答えた。それは本当のことだった。
「でもこの風の中、出航するのは愚かしさの極みだ。ねえ。君を不必要な危険にさらす
には、ぼくにはあまりにも君のことを大事に思ってるんだよ」
ぼくは、これをなかなか気の利いた結びだと思った。しかしエセルバーサは、こういう
事情だったら、火曜日まで乗船しに来なければよかったのに、と言って降りていってし
まっただけだった。
朝に、風はちょうどぐるりと向きをかえて、北向きだった。ぼくは早く起きて、この 観察をゴイルズ船長に告げた。
「アイ、アイ、サー」彼は告げた。「ついてねえですな。だがどうしようもありやせ
ん」
「ぼくたちは今日出発できると思わないかね?」いちかばちかぼくはあえて言ってみ
た。
彼は、ぼくに腹をたてたりはしなかった。ただ笑っただけだった。
「ようがす。旦那。もし旦那が行きてえのが、イプスウィッチだったら、これ以上のつ
きはねえってことでしょうなあ。だが目的地は、ご承知のとおり、オランダの海岸ちゅ
うわけでーーこうなっちまう訳ですよ」
ぼくはこのニュースをエセルバーサに告げ、その日は上陸して過ごすことに決めた。
ハーウィッチというのは、陽気な町ではないし、夕刻にかけては退屈と言
ってもいいだろう。我々は、お茶とクレスのサンドウィッチをドーヴァーコートでとっ
て、波止場にゴイルズ船長と船を求めて帰って来た。彼を一時間待った。帰ってきた船
長は、ぼくたちよりずっと
陽気だった。夜の当直の前は、あたためたグロッグ酒一杯の外には一滴だって飲みはし
ないと、船長自身が請け合わなかったら、ぼくたちは彼の事を酔っぱらいだとと思った
に違いなかった。
翌朝、風は南だったが、むしろゴイルズ船長は心配げになった。どうやら、これは移 動するのも、今いる所に泊まっているのも、同じくらいに危険だという徴らしかった。 唯一の希望は、何か起こる前に、風が変わることだけだった。この時になると、エセル バーサは、すっかり船を憎むようになっていた。彼女の言うところでは、個人的な意見 としては、一週間を海水浴用更衣車*の中で過ごし たほうがずっとましだった。少なくとも更衣車は固定されていることを考えれば。
我々はもう一日をハーウィッチですごした。そしてその夜と、次を。風はいまだに南 風だった。ぼくたちは、キングズヘッド亭に泊まった。金曜日には、風はまっすぐ西か ら吹いていた。ぼくはゴイルズ船長に、波止場で会って、この状況で、ぼくたちは出発 するべきだろうと、提案した。彼はぼくのしつこさに いらついたようだった。
「あんたが、もうちょいとでも海についてご存じだったらなあ、旦那」彼
は言った。「ご自分でも、こりゃ到底いかんってことがおわかりなんでしょうがなあ。
風は海から真っ向に吹いてきやすぜ」
「ゴイルズ船長。いったい僕が借りたこの物体はなんなのか、教えてくれない
か?これは帆船なのか、それとも屋形船なのか?」ぼくは言った。
船長はこの問いに驚愕したらしかった。
「こりゃ、ヨール大船檣と小船
檣を持つ小型帆船でさ」
「ぼくが聞いているのは」とぼく。「こいつはそもそもここから動かすことができるの
か、ということだ。それともここの据付の設備の一部なのかね?もしもなにかの設備な
のなら」さらに続けた。「率直に言ってくれたまえ。それならそれで、ぼくたちは鉢植
えの蔦を運んできて、舷窓に這わせるから。花を挿して日除けを甲板に置けば、素
敵な飾り付けになるだろうからね。だが、その反対にこいつを移動することができるの
だとしたら……」
「移動させる?」船長は遮った。「「荒くれ者」号にはちょうどいい追い風が必要なん
でさあ!」
ぼくは答えた「ちょうどいい風ってどんな風だい?」
ゴイルズ船長は当惑した顔をした。
「この一週間の間に」ぼくは続けた。「北風、南風、東風、そして西風が吹い
た。あいだの角度を含めてね。もし君が、これ以外に風が吹いて来る、羅針盤上に印さ
れた方角を知っているなら、教えてくれたまえ。そしたらその風を待とう。それができ
ないなら、そしてこの錨が大洋の底に根を生やしているんじゃないならば、今日出立し
て、どうなるのか見ようじゃないか」
船長は、ぼくの真剣さを了解した。
「ようがす。旦那」と言った。「あんたが
主人で、俺は部下だ。有難てえことに俺には子供が一人きりだ。そいつはまだひとりだ
ちしてねえんだけど。ありがてえことだ。旦那の遺言執行人も、年寄とったご婦人の面
倒をみてやるのが、連中の義務だとおお喜びでしょうや」
船長の重々しさに、ぼくは強い印象をうけた。
「ゴイルズさん」ぼくは言った。
「正直に言ってくれたまえ。天候がかわって、このいまいましい穴蔵から出ていけると
いう希望は、少しでもあるのかい?」
ゴイルズ氏の親切な親しみやすい態度が
戻ってきた。
「そりゃなあ、旦那」と言った。「ここはとても特別な海岸なんで。いったん外に出ち
まえば、なんの苦労もねえんだけれどよ。ここから、こんな貝の殻同然の浅底船で出帆
するってのはなあ、まあほんとのこと言って、うまいことだしぬいてやらなけりゃなら
ないわけなんでさ」
母親が眠る赤ん坊を見守るように、天候の様子に注意しておいてくれると保証するゴイ
ラス船長と別れた。これは彼が言ったとおりの例えで、ぼくはなかなか感動的だと思っ
た。彼をもういちど見たのは12時だった。船長は、「鎖と錨」亭の窓から、そいつを
真剣に見張っていた。
夕刻の5時に、突然、ぼくたちに僥幸が訪れた。ハイストリートの真ん中で、船乗りの
友人たちに出会ったのだ。かれらは舵の調子がわるいので、入港待機を余儀なくされて
いたのだった。ぼくが事情を話すと、連中は、驚くより面白がっているようすだった。
ゴイラス船長と二人の部下は、まだ天候を観察していた。ぼくはキングズヘッド亭にか
けこんで、エセルバーサに支度させた。ぼくたち四人はそっと埠頭に下りてゆき、船を
みつけた。見習い小僧が一人だけ船に残っていた。二人の友人は船を操縦して、六時ま
でには、ぼくたちは陽気に沿岸沿いを帆走していた。
夜にはオールドバラに入港した。翌日は、ヤーマスまで航海した。そこで、友人たちは
別れなければならなかった。ぼくたち二人は、船を放棄することにした。早朝にヤーマ
スの浜で、積み荷を半額で売り払った。ぼくは損をしたが、ゴイルス船長を「うまいこ
とだしぬいてやった」という満足を得られたわけだ。「荒くれ」号は、ソヴェリン金貨
数枚でハーウィッチまで回航する面倒をみてくれるという、地元の水夫のところに置い
てきた。そしてぼくたちは列車でロンドンに戻った。
この世には、「荒くれ」号以外のヨットはあるだろう。ゴイルス船長の外にも船乗りは
居るだろう。だが、この経験によって、ぼくは両者に偏見を持っているのだ。
ジョージもヨットを借りるのは荷が重すぎるという考えだった。ぼくたちはこの案を 退けた。
「河はどうだい」
ハリスが提案した。「前にも河でいろいろ楽しかったじゃないか」
沈黙のうちに、ジョージは煙草を噛み、ぼくはナッツをもう一つ割った。
「河も、昔とは違ってしまったからなあ」ぼくは言った。「正確にそれがなにかはわか
らない。でも河の空気の何かーー湿気かなーーのせいで、いつも腰痛が起こるんだ」
「ぼくもだよ」ジョージは言った。
「どうしてそうなるのかはわからない。でも、ぼくは最近、河の近くでは眠れないん
だ。春にジョーの所で一週間過ごしたんだけれどね、毎晩7時に目が覚めてしまって、
そのあとちっとも目がつぶれないんだ」
「ちょっと言ってみただけだよ」ハリスも述べた。「個人的に、ぼくにも向いていると
はいえない。関節によくないんだ」
「ぼくの身体に一番向いているのは」ぼくは言った。「山の空気なんだ。スコットラン
ドで徒歩旅行というのはどう思う?」
「スコットランドではいつも天気が悪い」ジョージが言った。「ぼくは一昨年むこうに
三週間居たけれど、いちどたりと乾いたドライな天気だったことは
ないぜ。つまり乾いたドライにはしらふという意味もあるというの
は天気のことだけれど」**
「スイスならいいんじゃないか」ハリスが言った。
「女たちが、ぼくたちだけでスイスに出かけるなんてことを許すと思うかい」ぼくは反
対した。「この間のことを忘れたのか。行くのなら、繊細な育ちのご婦人や子供が過ご
しにくい場所じゃなければだめだ。ひどいホテルとつらい旅、ぼくたちが苦労して、一
生懸命労働しなければならないような、腹がすいてすいて……」
「気をつけてくれ」ジョージがさえぎった。「すぐそうやって簡単に言う。ぼくも一
緒に行くことを忘れないでくれよ」
「わかった」ハリスが歓声をあげた。「サイクリングだ」
ジョージは疑わしそうな顔をした。
「自転車旅行だと、登り坂がたくさんあるぞ」とジョージ。「それに風は向かい風だ
し」
「ということは下り坂だってあるわけだ。追い風も」ハリスは言った。
「いままで気がついたことがなかったな」とこれはジョージ。
「君だって、サイクリング以上にいい考えは絶対に思い付かないぜ」ハリスが主張し
た。
ぼくはハリスの意見に傾きかけた。
「それに、場所についても考えがあるんだ」彼は続けた。
「黒森(ドイツ中部の森林地帯)だよ」
「なぜ?あそこは全部が登り坂だよ」ジョージが言う。
「全部じゃないさ」ハリスは言い返した。
「まあ、三分の二というところだろう。あと、一つ君が忘れていることがある」
用心深く周りを見回して、ささやくように声を落とした。
「登りには小さな鉄道
があるんだ。あのちっちゃな、歯車を使った鉄道もどきの……」
ドアが開いて、ハリス夫人が現われた。エセルバーサはもうボンネットをかぶ りかけたところですよ、と伝える。そしてミュリエルは、ずいぶん長いことぼくたちを 待った後で、ついに「気違い帽子屋のお茶会」をぼくたち抜きに披露してしまったの だった。
「クラブで、明日。四時」ハリスが立ち上がりながら、ぼくにささやいた。二階に上が る途中で、ぼくがジョージにそれを耳打ちした。
註
*海水浴用更衣車 ヴィクトリア時代の風物で、海岸に引 いていって中で着替えをする四角い箱車のようなもの。その無様さで有名なのは、ルイ ス・キャロルの「ジャバーウォッキー」にあるとおり。ここで、たぶん絵がみられま す。Click Here