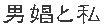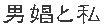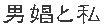
トモ子が実家に帰ったその日、わたしは実に半月振りに橋の上にいた。
定刻になると藤真が現れた。会いしなに、いつもの挨拶を抜きにして藤真は皮肉げに笑って云った。
「この前は随分なもてなしぶりだったっけなぁ。おかげで、この橋からの眺めにもほとほと嫌気がさしたよ」
「すまない」
トモ子が不意に帰国してわたしを空港に呼び出した時、実を云ってわたしは藤真と会う約束をしていたのだった。勿論わたしはトモ子を優先したのだから、藤真はこの橋の上で延々とわたしを待っていた訳である。幾度か気になりはしたが、家にとトモ子がいることも重なり今日まで連絡が出来なかったのだ。
わたしたちはホテルに向かった。浴室を使う前に、わたしと藤真はそれぞれ室内に位置を占め話した。
「恋人がいたのか」
わたしの説明を聞き終えて藤真は驚いた様子で云った。わたしはそれには答えずに云う。
「そういう訳で連絡出来なかった。悪かったよ。この埋め合わせは…」
わたしの言いかけた言葉を最後まで聞かずに藤真が遮った。
「全然気が付かなかったな。客の中でホモじゃないのはおまえだけだよ。女がいたなんてさ。おまえって普通の人だったんだね」
何故か感心したように藤真は云った。わたしのことをまるで今初めて見たというような顔つきで眺める。
「どういう意味」
呆れてわたしは云った。藤真は話題を変えた。
「でも、仕事辞めてどうするつもりなの」
「今朝実家に報告しに帰ったよ。元々悪いことを平気で出来るような人でもないからね。遅かれ早かれそうなっただろう」
「偉いね。おれなんかもう全然親と連絡取ってないなぁ。卒業する前からだよ」
藤真はベッドの端に腰掛けた恰好で云うとそのまま続けた。
「早いとこ帰った方がいいんじやないか?きっと事後報告の電話かなんかあるに決まってるよ」
わたしはその言葉に答える代わりに、ふと藤真にあることを云おうと思いついた。それは別に彼には関係のない事柄だったが、わたしは何故だか無性にそれを彼に伝えたい衝動に駆られていた。
わたしは実行した。
「結婚するんだ、近い内に」
一瞬、藤真は驚いて言葉もないようだった。だが、すぐ後に笑って云った。口調は変に納得しているようだ。
「そうだな。だっておまえももう三十二歳だもんなぁ。そのくらいの年のやつらはもうとっくに結婚して、子供の一人や二人いるって年齢だからな」
「藤真は結婚しないの」
わたしは好奇心で尋ねた。藤真はわたしを真っ直ぐに見つめ、それから目を逸らして思案していた。
「どうだろう。多分しないな。いや、出来ないんじゃないかと思うよ」
そしてわたしを見つめて、子供地味た笑顔になった。
「最近になって気付いたんだよ。もしかしたらおれは同性愛者かも知れないってさ」
「そうだからこの仕事してるんじゃないのか?」
藤真は首を振った。
「いいや。それは違うね。前に話したかも知れないけど、専門学校に通ってた頃に覚えたんだよ、こういうこと。おれはこれでも高校までは優秀な生徒だったからさ、健全だった訳だよ。でも美術系の学校に行くと、ああいう芸術に興味のある人間ってわりと道徳観薄弱なんだよね、知ってた?恰好も奇抜だし、中には普通のやつもいたけど、おれが仲良くしてたやつらはそういうんじゃなくて、結構外れたやつらだったのかもな、今考えると。月に一回は必ずパーティがあってね、一度しか行ったことないけど、あれは凄かった。酒池肉林って絶対あんなもんだよ。恋人がいようがいまいが、やり放題って感じだった。勿論、クスリなんかも出回っててね。何人かはそれで駄目になってくらしい。で、おれはそれっきりそのパーティには行かなかったんだけど、仲良くしてた友人が売春をしてたんだ。クスリ買う金が欲しくてね。デートクラブだったかな。ある日そいつは用事が出来てどうしても客と会うことが出来なくなったって、その役がおれのとこへ回ってきた。ただ話しをしてりゃいいって云われてさ、それならいいやって思ったんだよ。あっさり騙されたけどな。それがきっかけかな。だからおれはホモだと自覚してこれやってんじゃないんだぜ。面白半分でやってきたんだよ。楽だし、いろんなやつらと知り合って、そいつらと話しするのも愉しかったからね。でも最近、本当最近になって、自分にその毛があるんじゃないかって気付いたんだ。別に今更驚くこともないけど」
わたしはその話を聞いても、元々が藤真を同性愛者だと思っていた為に別段の感慨もなかった。
藤真はポケットから煙草を取り出した。わたしは云った。
「吸うなよ」
顔を上げて藤真はわたしを見た。わたしはソファに腰掛けると腕時計を確認して云った。
「先に使っていいよ」
そして背後の浴室を指した。藤真は暫くわたしを見ていたが、干渉は無用と思ったのか何も云わずに浴室に向かった。
その間わたしは、トモ子のことを考えていた。これから短い夏の休暇が始まる。その後、秋に近付いた時期に結婚をしようと思った。何故という理由はないが、そのくらいが妥当だろうと感じたのだ。女性から求婚されるというのは、事実わたしの趣味ではなかった。わたしは古風な考え方があって、それは男性から云って然るべきものと常々思っていたのだ。正直に云ってトモ子との結婚を考えたことはないが、云われてみれば三年以上も付き合っているわたしとトモ子の関係上、この先にあるものは結婚以外にないのだった。
わたしは結婚というものに別段の憧れはない。だからこそ、彼女との結婚を承知出来たし納得もした。結婚した後は、こうして男娼を買う真似は経済的に不可能な為、藤真とも会うことはないだろうと漠然と考えたが、その時に浴室から彼が姿を見せたのでわたしの考えは中断され、わたしもまた固執しなかった。
何を考えているのかとわたしは問う。それと同時に定期的なスプリングの軋みが途絶えた。ぼんやりとしたベッドスタンドのほの暗い明かりに照らし出された藤真の瞳はじいっとわたしを見つめ、それから咳払いをして云った。
「悪い。そういうつもりじゃなかったんだけどさ。気が散った?」
「いいや。何を考えてたのか知りたいと思っただけだよ。何か考えてたろ?」
わたしは藤真に覆い被さるような姿勢を解くと、空いているベッドのスペースに身体を横たえた。煙草をくわえて火をつける。
「こういう仕事をする上で、何が一番まずいかって知ってるか?」
顔だけをこちらに向けて藤真は云った。
「なに?病気?」
わたしの返答に藤真は失笑した。おまえらしいね、と云う。
藤真は煙草を吸えない代わりに側にあったミネラルウォーターを一口飲んでいた。
「違うよ。相手の私生活を聞くことだよ。趣味の話やそんなもんはいい。でも私的な、もの凄く私的な話題は普通はしないもんだよ。分かる?お互いの為にその方がいいからな」
「かも知れないな」
何を云いたいのか理解出来ずにわたしは適当に返答した。
「おまえが今おれにしてるようなことをさ、他の誰かにもしているんだってことが頭の中に居座っちゃってね。なんだか妙な気持ちになってたんだよ」
「妙なってどんな」
わたしは鸚鵡返しに尋ねた。藤真は天井を向いて暫く沈黙した。
「だから妙なんだよ。他にどう云ったらいいか…居心地が悪いって云うか、そんな感じさ。うまく説明出来ねえけど」
「へえ。ナーバスな時期なのかな」
人事のようにわたしは云っていた。わたしはと云うと、藤真が今云ったような感覚を味わう機会には巡り会わなかった。男娼を抱く時に、その男娼が他の男たちにどう抱かれているか等という事柄がわたしを苦しめたことはないし、反対にそれによって興奮するようなこともなかった。また、トモ子と彼を重ねるようなこともない。
不思議とわたしは倫理的観念に乏しいのか、罪悪感は湧き起こらなかった。わたしはこの行為を完全に事務的なものだと理解していた。女性には理解出来ない、必要な処理だと思っている。金を払う事実がわたしにそう思わせているのかも知れなかった。しかしわたしは同時に幾人もの人間を愛することも可能だと思えたし、また愛していない者とセックスをすることも十分に可能であり、快楽は感情とは別に与えられると思っていた。
そして愛情のない人間とも一生を共にすることも可能だと信じていた。
わたしはそういう人間だった。
「これは?」
わたしは横たわっている彼に向き直り云った。
藤真は首を振った。
わたしは別の行動をした。
藤真は再び首を振った。
彼の開いた両脚の間に、刺激を与えた時にのみ、藤真は僅かに反応した。
わたしは顔を上げ藤真に云った。
「想像力が欠如してるんじゃないか?」
藤真は肩を竦めた。
男娼を商売としながら、藤真は性器に与えられる直接的な刺激以外には鈍重な反応しか示さない。わたしは藤真のそこが好きだった。
わたしが藤真を抱く時、わたしはこの世の中でたった一人のような気持ちになる。わたしはまるで、セックスを覚えたての中学生のように相手の都合を無視して己の快楽を追求する惨めな少年のようだった。淫靡な妄想に駆られ畜生と化した一人の男のようだった。わたしは、無反応の人形に対して自分に必要なだけの官能を引き出すことの虚しさを十分知っていた。しかしそのことが、より自虐的な甘い官能をもたらそうとは、今迄知らずにいた。人間には元来、自愛の念が強くあるのだ。そしてそれと同時に、マゾヒズムとサディズムも同等に備わっているのだ。わたしは藤真を抱く時に、その全てを与えられていた。わたしという一人の人間の男としての本能を甘く満たす征服欲、そして快楽を分かち合えない虚しさ、その二つは混在し、巧みに絡まり合って独特の感覚をわたしに感じさせた。
実体が伴った自慰なのだ。
「乱暴になったんじゃないかって云われたよ」
「誰に?」
藤真は尋ね、それからすぐに意味を理解したようだった。
わたしは、トモ子にそう云われていた。女性には、特にトモ子のような女性には多分のマゾヒズム傾向が内在しているから、彼女はそれを嬉しそうだったが、わたしが乱暴になったか否かの真偽はさておいても、それは不感症の男娼を長く抱いていたせいであり、決して男性的本能をトモ子に刺激されたからでも、ましてや長年蓄積した欲求をやっと解放した結果でもないのだから、わたしはトモ子が勝手に勘違いをし尚悦んでいるのを見て、寒々しい気持ちになった。
「あんたのせいだぞ」
わたしは責めるでもなく、ただ単に、こう云ったら相手が何と云ってよこすかという好奇心に従って云ってみた。
藤真は横たえた身体の上半身だけを起こし、両肘で身体を支えた態勢でわたしを見て笑った。
「そうかな、おまえ乱暴かな。もっと酷いのも大勢いるけどね。一応は金貰ってるし、演出しなきゃなんないから他の客の時はこうじゃないにしても、大抵は自己陶酔で終わってるやつら多いぜ。それなのにおまえはわりかし丁寧な方に入ると思うけどなぁ。よくは知らないけど。ただセックスって確かに性格出るよな」
「ふうん。じゃあおれの性格は一体どうなんだ?」
わたしは藤真の自信ありげな態度を鼻で笑って問う。藤真は意地悪い顔つきでわたしを見て云った。
「抜け目ない感じ?技術を追求し過ぎて感情がないって感じだな、おまえは」
わたしは何も云わなかったが、口元だけで笑った。
「その様子じゃ図星だろう?」
唇を歪めて藤真は笑った。本当に憎らしい顔つきだ。
「どうだか。大体、感情移入が必要だとは思わないがね」
「バァーカ」
藤真はせせら笑うように云った。わたしが憤慨を表す前に藤真は口を開いた。
「前に云ったっけな。客の中で一人、おれに毎日手紙を送ってくるやつがいるんだ。まだ若いんだぜ、確かおれより三つ上で二十四歳かな。そいつはどうやら手紙の内容によるとおれのことが好きみたいだ。だからおれはそいつと会うのやめた。そういう風になったら駄目なんだよ。同じ行為をするんでも、そこに感情があるかないかでは全然別のものになるのさ。金のやりとりがある以上は、向こうはおれに構わず勝手にやってくれりゃあいいんだよ。だけどそいつは違うんだ、必死なんだよ。おれに好かれようってさ。あるいは、おれをいかせようってね。それは考えられない程の負担だぞ。こっちは金しかいらないんだから、他の感情を捧げられたって迷惑なんだ。つまり、そういうことさ。恋愛が絡むかどうかで、同じ行為でも全然別物ってことなんだよ」
「要するに、もしこっちに何らかの感情があればあんたはすぐ分かるって訳か」
「ああ、多分ね」
わたしは笑った。
「確信めいた口調だね」
藤真はその言葉に笑わなかったがこう云った。
「だってそうじゃなきゃおかしいだろ。好きなやつと嫌いなやつに同じ態度取る人間いるか?普通は違うだろ。だったらセックスも同じだと思うけどな。大事に思ってるかどうかで、微妙に違う筈だよ」
「じゃあ売春っていうのも案外寂しい商売なんだな。金は手には入っても、結局体よく利用されてるだけじゃないか」
「まあね。これは仕事だから」
「犯罪だぞ」
わたしの言葉に藤真は微笑した。
そうやって幾度か行為を中断しながらもわたしたちはセックスをした。夜の十時過ぎにわたしと藤真はホテルを出た。わたしは彼に先日約束を反古にした詫びとして、その分の代金も支払うと云ったが、藤真は辞退し、その代わりに何か食事を食べさせてくれと頼んできた。云われた通り、わたしは彼に食事をご馳走した。
わたしはトモ子と恋愛をしているとは思わない。しかしトモ子を嫌いかと云えばそうでもない。
わたしは大抵の人間とは上手く付き合える方だった。我を通そうとはしないから口論をすることも殆ど経験がない。
わたしはトモ子を愛してはいないが、結婚をしてもよいと思っている。トモ子はわたしを愛しているから結婚をしたいと思っている。わたしは、自分が相手を愛していないのに相手から愛されることに対して負担を感じないたちであった。わたしには元々良心というものが乏しいのだ。わたしは随分利己的に生まれついているから、他人の真心に背いた行為や感情を例え自分が持っていたとしても、それを罪悪だとは考えなかった。
わたしは一番に自分自身のことを大切に思っている。それ以外のことには無関心だった。故にわたしは優しいふりをすることに長けていた。よそ事だと思えばこそわたしは他人に対していくらでも優しく振る舞えた。
わたしには義務感があった。しかしそれも現実的な意味においてしかその役割を果たさなかった。精神的な目に見えない関わりに対してわたしはいかなる義務感も抱かなかった。わたしは世間的に結婚という立場に置かれた時、わたし自身が決して妻を哀しませるような事をしはしないだろうと思っている。反対に云えば、それさえしなければ妻がわたしに寄せる愛情にわたしが愛情で答える義務はないと思っている。
わたしは人を愛することがないから、人がわたしを愛することに無関心だった。
トモ子と正式に結婚をすることに決定した。式の日取りは九月の中旬の大安吉日となった。トモ子は現在実家で家事手伝いをしている。既に招待客の大凡の名簿を作っていた。客は全てで四百人程になった。式場は都心のホテルに決まり、トモ子は毎日母親と衣装の選定に忙しい。それから半月程度の旅行に行くことになった。イタリアを始め、地中海付近の国々を旅行する。わたしはかねてからの貯金と、先年父が亡くなった際に相続した遺産も莫大に口座に残っていたから、都心部に一軒家を買った。勿論、それはトモ子との新婚生活を送る為のものだった。色々手配して、家具や調度品も全て先に新居へ運んで貰うこととした。
夏の休暇が訪れたが、不運にもトモ子は体調を崩し家庭で療養していた為に、わたしはその間ずっと自分の自由に時間を使うことが出来た。不要な家財道具などは早めに処分しようと室内を片付けている時、ふとわたしはあることを思いついた。その考えは唐突にわたしの脳裏に去来した。アルバムに紛れ込んでいたいつか昔の旅行のパンフレットを見た時に、わたしはそれを思いついたのだ。すぐに実行に移した。
|| NEXT ||
|| 伽藍堂 || 煩悩坩堝 ||