日本のターボトレイン
ガスタービン機関車
世界では鉄道へののガスタービン応用が機関車から始まりましたが、日本では計画もなかったようです。
昭和40年代すでに国鉄貨物の斜陽化が兼著となっており、DD51すら持て余そうかという時期になっていたため、非電化線区に強力な機関車の需要はなかったのです。
JR貨物の時代になってDD51重連牽引の解消とスピードアップのために強力な機関車が必要となりましたが、すでに交流電気式のディーゼルで対応できる時代となっていましたからこの方式のDF200が誕生しました。
もし昭和40年代の国鉄時代に貨物輸送の主役が鉄道でありつづけていたら、EF66に相当する高性能の電気式ガスタービン機関車が計画されたかもしれません。 しかし、ユニオンパシフィック鉄道と同じようにその後の高性能高効率ディーゼル(DF200クラス重連で対応できる)の登場に押されて引退の道を歩んでいたことでしょう。
ガスタービン動車
120km/h運転 昭和30年代後半から従来のディーゼル動車 に代わる高性能気動車として開発されていた91系、181系が昭和40年代初期に実用化され、特別な勾配線でなければ当時の電車特急なみの俊足を非電化区間で誇っていました。 しかし、在来線の最高速度は昭和43年に120km/h(181系に
に代わる高性能気動車として開発されていた91系、181系が昭和40年代初期に実用化され、特別な勾配線でなければ当時の電車特急なみの俊足を非電化区間で誇っていました。 しかし、在来線の最高速度は昭和43年に120km/h(181系に よる気動車初の120km/h営業運転は「しなの」営業開始の時と誤解されている向きがありますが、実際は昭和45年秋の「つばさ」高速化からです。「しなの」は120km/h試験のみで、営業速度は95km/hにとどまっていた)に達し、信号の関係で限界に近づいてきました。 そこで曲線通過速度向上に主眼が移り、昭和45年に登場したのが591系高速運転用試験電車でした。
よる気動車初の120km/h営業運転は「しなの」営業開始の時と誤解されている向きがありますが、実際は昭和45年秋の「つばさ」高速化からです。「しなの」は120km/h試験のみで、営業速度は95km/hにとどまっていた)に達し、信号の関係で限界に近づいてきました。 そこで曲線通過速度向上に主眼が移り、昭和45年に登場したのが591系高速運転用試験電車でした。
ディーゼルの限界 一方、非電化線区用にも同様な高速車両が望まれていました。 非電化線区では電化区間と比べると線形が厳しく、181系では高速運転できず、より軽量で低重心、加速性能のよい列車が望まれていました。 しかし、当時のディーゼルエンジンでは181系クラスが限界に近く、さらなる軽量化、大出力化は望めませんでした。 この限界を打破するために注目されたのがガスタービンです。
試験車登場 昭和41年より基礎的な研究が始まり、昭和43年にはキハ07に動力装置を搭載、翌年には磐越東線で走行試験が行われました。
この試験車は床下に小さなエンジンと大きな給排気装置を積んでいました。 はじめてその姿を見たとき、300馬力ほどのありふれた性能の気動車だろうと思いましたが、実はそのエンジンは1000馬力以上もあったのです。 なんと床下に連続定格1050 馬力(最大1250馬力)のガスタービンが搭載されていました。 毎分二万回転近くで回るタービンはディーゼルの数十分の一の大きさしかなかったのです。 トン当たり出力は30馬力に達しました。 そして最高速度は150km/hというとんでもない設定だったのです。
馬力(最大1250馬力)のガスタービンが搭載されていました。 毎分二万回転近くで回るタービンはディーゼルの数十分の一の大きさしかなかったのです。 トン当たり出力は30馬力に達しました。 そして最高速度は150km/hというとんでもない設定だったのです。
(リンクのページにあるジェットバイクに搭載されているエンジンがこれとほぼ同クラス同サイズですから、バイクに乗った人と比べると大きさがよくわかるでしょう。)
キハ07はなんと7倍ものハイパワーを与えられスーパーカーに変身したのです!
この気動車の恐るべき性能は未だに破られていない日本最強、狭軌で設計された気動車としては世界最強最速だったのです。 加速余力は十分ですから速度向上試験をもしやっていたら優に160km/hを超えていたはずで、未だに破られることのない国内気動車最高記録を樹立していたでしょう(台上試験では153キロで連続性能試験が行われた。 これまでの実走行の気動車最高記録は平成1年に183系の改造車(出力向上、減速比変更)が樹立した153.5km/h)。 当時、いかにガスタービン車への期待が大きかったかがうかがえます。
実際の走行試験は磐越東線で行われました。 しかも最高速度は在来車と同じ、たったの85km/h。 速度が遅いほど燃費が悪くなるガスタービン車をのろのろ運転。 しかも重いキハ58を1両エンジンカット状態で従えてのろのろ走ったたわけで、ディーゼル動車の2倍ほど燃料を食ったようです。
その翌年にはガスタービンを別機種とし、減速比を大きくしたうえで床上に搭載し同一区間で試験が行われました。 ただし、このときは減速比が大きいためこの車両がはいていたキハ181系の2軸駆動の動台車では空転してしまうため、出力を800馬力に絞って走行試験が行われました。

高速運転用試験気動車 昭和47年、いよいよ591系高速運用試験電車の非電 化区間版として391系高速運転用試験気動車が登場しました。 当時は推進軸のねじれの問題が解決しておらず、車体に搭載したエンジンからどうやって車軸に動力を伝えるかが問題でした。 そこで中央に客席のない振子しない小さな動力車をはさみ、両端に連接式の振子可能な付随車を中バリを介して配置したユニークな構造の車両となりました。
化区間版として391系高速運転用試験気動車が登場しました。 当時は推進軸のねじれの問題が解決しておらず、車体に搭載したエンジンからどうやって車軸に動力を伝えるかが問題でした。 そこで中央に客席のない振子しない小さな動力車をはさみ、両端に連接式の振子可能な付随車を中バリを介して配置したユニークな構造の車両となりました。
中央の小さな動力車はコンパクトながら定格1050馬力(最大1250馬力)のガスタービンを搭載していました。設計速度は130km/hとさすがに燃費を考えて150km/hという遊びは控えました。 しか し、591系試験電車や181系気動車と同じデザインの運転台にはちゃんと特急電車と同じ160km/hまで刻まれた速度計が鎮座して
し、591系試験電車や181系気動車と同じデザインの運転台にはちゃんと特急電車と同じ160km/hまで刻まれた速度計が鎮座して いたのです。
いたのです。
当時、気動車用の大容量液体変速機はありませんでした。 しかし、ガスタービンは回りはじめの回転力が最大出力時の約2倍と大きく、低速域での加速性能が不足するものの変速機なしで運転は可能です。 こうして本格的直結無段変速気動車が誕生しました。 液体変速機の省略だけでも数トン軽量化でき、アルミ車体とあいまって特急用車両でありながら編成全体で運転整備重量が70トンを切る69.5トンとなったのです。 これは従来の特急用電車、気動車の80〜90トンと比較すると大幅に軽量で、軸重は8〜10トンと591系より1〜2トン軽量化され、線路構造の弱い線区での高速走行に適していました。 
連続定格の出力設定であったとしても、この性能は現在の高性能気動車さえ上回るもので、各種の損失を除外した、実際の走行に利用できる有効な出力(動輪周出力)はトン当たり12馬力に迫り、281系気動車を1馬力ほど引き離しています。
試験車の関係か、手抜きされた前面形状とデザインはお世辞にもかっこいいと言えるものではありませんでしたが、技術的には日本の気動車の歴史においてもっとも革新的な気動車だったのです。
この車両は春に川越線での試運転の後、伯備線で足慣らしを行なった後、曲線通過速度25km/h向上、最高速度130km/h、山陽線での分岐器130km/h通過試験、騒音測定、速度向上試験(140程度まで、タービンのレブリミッタにより制限されていた)などが行われました。
この間、トンネル内での起動で排気ガスが吸気側へ回り込みエンジン過熱による起動失敗や起動時の高騒音、滑走検出再粘着装置(車で流行っているABS)の不具合、クラッチの故障などのトラブルが生じました。 そこで排気ガスの案内板の設置、クラッチの廃止による直結駆動、燃料噴射装置の改良によるラグの短縮などの改造が行われ、昭和48年冬には田沢湖線での耐雪試験が行われ、量産試作車へのデータが収集されました。
量産車登場間近 この間、どのような編成にするか、各種の案が出ていました。 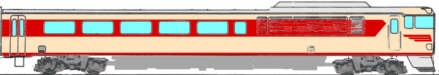 ガスタービン車の計画が始まったころには181系の運転席後方の機械室に2200馬力程度のガスタービンを搭載した動力車を両端に配し、中間に軽量の付随車を6〜7両ほど組み込んだプッシュプルタイプの動力集中方式の列車が構想されました。
ガスタービン車の計画が始まったころには181系の運転席後方の機械室に2200馬力程度のガスタービンを搭載した動力車を両端に配し、中間に軽量の付随車を6〜7両ほど組み込んだプッシュプルタイプの動力集中方式の列車が構想されました。 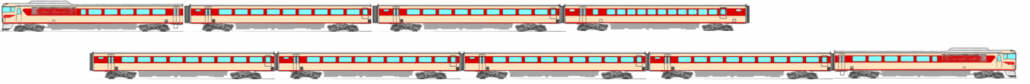 181系は先頭車に合計730馬力ものディーゼルエンジンを積んでいますから、2200馬力のガスタービン車のほうがかえって軽量になります。 変速機がないとはいえ、なにしろ2000馬力超、あまり軽量になると全軸駆動でも空転が多発します。 おそらく軸重10トン程度を目安に設計されたでしょう。 なんと40トン程度でDD51と同じ出力を持つ、機関車ではない、気動車が計画されていたのです(伝達効率の差で高速域の動輪周出力はガスタービン動車のほうが2割近く上回った! 客席もキハ181並かやや少ない程度確保されていた!)。 この方式は分割併合や輸送量に応じての編成両数の自由度がありませんが、線形に応じて付随車を増減して性能面の対応ができる利点はありました。
181系は先頭車に合計730馬力ものディーゼルエンジンを積んでいますから、2200馬力のガスタービン車のほうがかえって軽量になります。 変速機がないとはいえ、なにしろ2000馬力超、あまり軽量になると全軸駆動でも空転が多発します。 おそらく軸重10トン程度を目安に設計されたでしょう。 なんと40トン程度でDD51と同じ出力を持つ、機関車ではない、気動車が計画されていたのです(伝達効率の差で高速域の動輪周出力はガスタービン動車のほうが2割近く上回った! 客席もキハ181並かやや少ない程度確保されていた!)。 この方式は分割併合や輸送量に応じての編成両数の自由度がありませんが、線形に応じて付随車を増減して性能面の対応ができる利点はありました。
その後、391の試作が決まると、同型の連接構造を1ユニットとし、3ユニットから6ユニット で1編成を構成する案が登場しました。 しかし、この方式では山岳線でも平坦線でも性能が同一になる点や、変則的な連接構造のため車体長が在来車と一致せず、ホームなど接客施設の面で問題がありました。 電車でも結局は591系の連接式をやめて381系が誕生した経緯もあって通常の車体を採用する方向で計画が進んだようです。 伯備線程度であれば4M5Tから5M6T程度、より平坦線の場合は3M6Tから4M7T程度で対応するつもりだったようです。 当然、M車1両の出力は1000馬力から1200馬力程度に達し、エンジンの床下搭載か、車端搭載を想定していたようです。 振子車で大トルクをどうやって伝達する予定だったか興味ある話です。 391の中バリ方式を用いて駆動系と車体を独立させようとしたのでしょうか。
で1編成を構成する案が登場しました。 しかし、この方式では山岳線でも平坦線でも性能が同一になる点や、変則的な連接構造のため車体長が在来車と一致せず、ホームなど接客施設の面で問題がありました。 電車でも結局は591系の連接式をやめて381系が誕生した経緯もあって通常の車体を採用する方向で計画が進んだようです。 伯備線程度であれば4M5Tから5M6T程度、より平坦線の場合は3M6Tから4M7T程度で対応するつもりだったようです。 当然、M車1両の出力は1000馬力から1200馬力程度に達し、エンジンの床下搭載か、車端搭載を想定していたようです。 振子車で大トルクをどうやって伝達する予定だったか興味ある話です。 391の中バリ方式を用いて駆動系と車体を独立させようとしたのでしょうか。
しかし、残念ながら昭和48年のオイルショックと国鉄経営、労使関係の破綻も手伝って現実の量産車は日の目を見ることはありませんでした。
オイルショックがなかったら もし、オイルショックがなかったか、あるいはもう少し遅れていたら、確実に量産車が登場し営業列車として走っていたでしょう。
当時最初の投入予定線は伯備線が候補となっており、その後、紀勢線、田沢湖線が並んでいました。 結果がよければ予讃線、土讃線も可能性があり、北海道各線も有力な候補となったでしょう。
伯備線では分岐器改良なしで米子-岡山間の到達時分は2時間10分、分岐器改良と併せて2時間となる予定で、現実の世界の出来事より10年以上も先行したスピードアップの可能性を秘めていたのです。
他の線区でも同様で、当時は財政的に積極的な軌道強化はできなかったでしょうからJR時代と同等とはいかないまでも、現在の高性能の振子気動車がもたらしたスピードアップに近いものが各地で昭和50年初頭に達成できていたはずです。 まだ地方には高速道路がほとんどない時代、幹線道路すら未整備の時代ですから、地方鉄道の高速化はそれなりの効果を持っていたでしょう。
トップページ

 に代わる高性能気動車として開発されていた91系、181系が昭和40年代初期に実用化され、特別な勾配線でなければ当時の電車特急なみの俊足を非電化区間で誇っていました。 しかし、在来線の最高速度は昭和43年に120km/h(181系に
に代わる高性能気動車として開発されていた91系、181系が昭和40年代初期に実用化され、特別な勾配線でなければ当時の電車特急なみの俊足を非電化区間で誇っていました。 しかし、在来線の最高速度は昭和43年に120km/h(181系に よる気動車初の120km/h営業運転は「しなの」営業開始の時と誤解されている向きがありますが、実際は昭和45年秋の「つばさ」高速化からです。「しなの」は120km/h試験のみで、営業速度は95km/hにとどまっていた)に達し、信号の関係で限界に近づいてきました。 そこで曲線通過速度向上に主眼が移り、昭和45年に登場したのが591系高速運転用試験電車でした。
よる気動車初の120km/h営業運転は「しなの」営業開始の時と誤解されている向きがありますが、実際は昭和45年秋の「つばさ」高速化からです。「しなの」は120km/h試験のみで、営業速度は95km/hにとどまっていた)に達し、信号の関係で限界に近づいてきました。 そこで曲線通過速度向上に主眼が移り、昭和45年に登場したのが591系高速運転用試験電車でした。  馬力(最大1250馬力)のガスタービンが搭載されていました。 毎分二万回転近くで回るタービンはディーゼルの数十分の一の大きさしかなかったのです。 トン当たり出力は30馬力に達しました。 そして最高速度は150km/hというとんでもない設定だったのです。
馬力(最大1250馬力)のガスタービンが搭載されていました。 毎分二万回転近くで回るタービンはディーゼルの数十分の一の大きさしかなかったのです。 トン当たり出力は30馬力に達しました。 そして最高速度は150km/hというとんでもない設定だったのです。 し、591系試験電車や181系気動車と同じデザインの運転台にはちゃんと特急電車と同じ160km/hまで刻まれた速度計が鎮座して
し、591系試験電車や181系気動車と同じデザインの運転台にはちゃんと特急電車と同じ160km/hまで刻まれた速度計が鎮座して いたのです。
いたのです。 
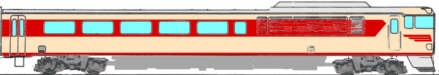 ガスタービン車の計画が始まったころには181系の運転席後方の機械室に2200馬力程度のガスタービンを搭載した動力車を両端に配し、中間に軽量の付随車を6〜7両ほど組み込んだプッシュプルタイプの動力集中方式の列車が構想されました。
ガスタービン車の計画が始まったころには181系の運転席後方の機械室に2200馬力程度のガスタービンを搭載した動力車を両端に配し、中間に軽量の付随車を6〜7両ほど組み込んだプッシュプルタイプの動力集中方式の列車が構想されました。 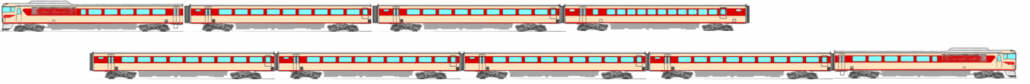 181系は先頭車に合計730馬力ものディーゼルエンジンを積んでいますから、2200馬力のガスタービン車のほうがかえって軽量になります。 変速機がないとはいえ、なにしろ2000馬力超、あまり軽量になると全軸駆動でも空転が多発します。 おそらく軸重10トン程度を目安に設計されたでしょう。 なんと40トン程度でDD51と同じ出力を持つ、機関車ではない、気動車が計画されていたのです(伝達効率の差で高速域の動輪周出力はガスタービン動車のほうが2割近く上回った! 客席もキハ181並かやや少ない程度確保されていた!)。 この方式は分割併合や輸送量に応じての編成両数の自由度がありませんが、線形に応じて付随車を増減して性能面の対応ができる利点はありました。
181系は先頭車に合計730馬力ものディーゼルエンジンを積んでいますから、2200馬力のガスタービン車のほうがかえって軽量になります。 変速機がないとはいえ、なにしろ2000馬力超、あまり軽量になると全軸駆動でも空転が多発します。 おそらく軸重10トン程度を目安に設計されたでしょう。 なんと40トン程度でDD51と同じ出力を持つ、機関車ではない、気動車が計画されていたのです(伝達効率の差で高速域の動輪周出力はガスタービン動車のほうが2割近く上回った! 客席もキハ181並かやや少ない程度確保されていた!)。 この方式は分割併合や輸送量に応じての編成両数の自由度がありませんが、線形に応じて付随車を増減して性能面の対応ができる利点はありました。