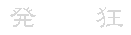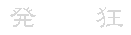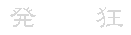
まるで怒ったかのような顔をしてHはおれの前に立っていた。
あいつの苦悩をその顔は如実に表していた。
おれにこっぴどい厭がらせでも受けたといいたげなHの表情・・・
風が吹いて冷たい瞳がおれを映していた。
聞こえてくる声の中で何かが死んでしまった。
おれも、そしてHもそれを感じているのだろう。
かつて何かが生まれたのだという証拠に、今何かが死んでいく。
おれは誰にも責任を求めたりしない。
これは一つの真実だ。決して避け得ない結果だ。
おれは衰えを感じている。
愛や情熱という言葉で表される、ある一つの感情が静かに衰えていく。
おれの中ではもう愛情というものが完全に抹殺されてしまったのだろうか。
何もかもぼんやりと原型を留めない。
もしおれがHにかつて抱いていた感情を今は抱くことが出来ないというのなら、
おれはもっと晴れ晴れとした気持ちでHの視線に応じていられる筈ではないのか。
もし仮に、
時の経過と共に誰かを愛せなくなる・・・全く愛せなくなる時があるというのなら、
何故おれにそれが分からないのだろう。
そしてHにはそれが分かっているのだろうか。
おれにはHを愛していたという記憶がある。
だがそれだって、おれが勝手に作り上げた妄想とも言うべきものなのかも知れない。
はっきりとしたことは何もかも分からない。
おれには、以前愛していたような記憶があるだけだ。
そして今はそれがないような気がするだけ。
たがこれもまた錯覚というものなのかも知れない。
Hはおれを見ている。
おれもHを見つめている。
まるで見るものはそれしかないというように、Hを見ている。
そして実際には何も見てはいない。
おれは・・・おれは確かに混乱していた。
おれは何かを知っているが、それは果たして本当のことなのだろうか。
おれは何かを失ったような気がするが、本当にそれはおれの手の届かないところへ行ってしまったのか、
そしてそれは以前おれの手の中にあったものなのか。
どうしたんだ、とHが声に出して言った。
おれはそれを聞いた。
はっきりと耳に入った。
それなのに、それについて考えることが出来ない。
思考力が低下しているように、
そしておれの意識は深淵の最も深い奥底で燻り続ける。
なんでもないとおれは言った。
言ったような気がする。そんな声を聞いた気がする。
Hは顔色一つ、眉一つ動かずにおれを見たままだ。
おれの言ったことが聞こえなかったのだろうか。それともおれは本当にそう言ったのだろうか。
おれは今どんな顔をしているだろう。
Hの冷たい顔を見返すおれは、どんな風にやつの目に映るだろう。
おれは混乱していた。
それはHが、おれたちはもう終わりだ、ということを仄めかしたせいではない。
それは・・・そんなことは前から分かっていた。
ではおれは何を混乱しているのだろう。
おれは・・・おれがHを愛しているか、いないのか、愛していたのか、いなかったのか、それが分からなくなってしまった。
そんなことがあっていいものか。
Hをどう思っていたか忘れたなんて?
だが、思い出せない。
おれは自分自身を見失ったようだ。
おれの神経は麻痺したようになっていて、感情というものが突如として自分から消えてしまったもののように、
おれには手応えというものがない。
Hは何を考えているのか。
おれに教えて欲しいくらいだ。
おれがどんな顔をしてどんな言葉を言えばいいのか、あいつなら分かっている筈だ。
そして何故それを教えてくれないのだろう。
おれは忘れてしまった。
かつての自分が何をしていたかなんて。
この瞬間。
Hと面と向かってこうして立ち尽くしているこの時に、闇に浮かぶ月明かりの頼りない光の下で、おれは・・・
分からない。
自分が何をすべきか。
何かが消えていく。
おれとHの間に立ちはだかる闇は何なのだ。
これは本当に闇なのか。
おれたちはどうやら元には戻らないらしい、Hの声。
Hは何故こんな顔をして、こんなことを言うのだろう。
どういうつもりで言うのだろうか。
読めない。
お前が見えない。
そう。
元には戻らないだろう。
おれは元なんてものを忘れてしまったのだから。
元に戻る道を、自分たちが何処からやって来たのかを忘れてしまったのだから。
しかしこれがこの場合、どれほどの問題なのだろうか。
元へ戻ることが一体何だというのだろう。
おれがすべきことは、こいつを愛しているのかいないのかを知ることだ。
どうやってそれを知ろう。
何故そんなことが分からないのだろう。
おれは迷っている。
おれは変化していない。
Hも何も変化してはいない。
それなのに、何が変化してしまったのだ?
そしてもう二度とは元に戻らないものとは?
おれを愛していないんだな。
Hは迷惑そうな表情をちらと浮かべた。
ぼんやりとした月明かりでは見える筈もないと思ったのだろうが、おれは見逃さなかった。
確かにやつは、一瞬顔を歪めた。
そして、
そういう問題じゃない。その問いにどうしても答えろというのなら、おれはきっとお前を愛している、
と言った。
暗唱するような言葉の流れ。すらすらと淀みなく。
Hは苦痛そうであった。
それはどんな苦痛か。
何故顔を歪めて、おれを愛していると言わねばならないのだろうか。
もしかするとおれの顔も歪んでいるのかも知れない。
つまりHにとって、おれを愛していることは既に一種の苦痛となった訳か。
そしておれはHを愛しているかどうか断言出来ないでいる。
自分の気持ちが説明出来ないでいる。
ということは・・・
そうだ、もう終わりだ。
おれははっきりと言った。
その筈が、耳に届くおれの声は奇妙に上擦って、おまけに震えて弱々しく、今にも泣きだしそうだった。
Hはまたしても顔を歪めた。
今度は隠そうともせず、露骨に歪めてみせた。
薄笑いのようなものがその顔の上をかすめたが、本当のところは分からない。
おれはどんな顔をしてやつを見ているだろう。
おれは・・・おれは今ちゃんと立っているのか?
愛しているかなんてもう問題ではないと言いたげなHを見ているとおれもそう思えた。
愛していようがいまいが、もう元には戻らない。
そして元に戻らないということが全てを駄目にしてしまうらしい。
そうだ。
おれたちはもう元には戻れず、そしてHももうおれのことを見ていないかも知れない。
愛してもいず、
憎んでもいず、
恨んでも、
必要でも何でもないかも知れない。
ただ、それだけのことかも知れない。
だがおれは煮え切らないでいる。
Hはそれでもおれにとって、
壁や空気や他人とは違うある意味を持っている人間なのだ。
何故?
どうせこれだっておれの妄想かも知れない。
本当は虫けらのようにしかあいつを考えていないのかも知れない。
錯覚なのかも知れない。
しかし・・・何故だろう・・・Hを見ているといや、正確にはおれは見ていないし、見えていないが、Hを感じる。
この感じるということは一体・・・?
おれたちは別れるんだな。おれが言った。
不自然な響きを伴って空気に消えた。
おれの声はどうしてこんなにか細くも今にも消え入りそうなんだ?
おれはずっとこんな喋り方をしていたのだろうか・・・
Hは顔を背けた。
おれはHがそうしたことに驚いた。
Hがそう出来ることを考えもしなかった。
おれたちは見つめ合うことしか出来ないように思っていたが・・・
別れるといっても、どの程度別れられるか・・・別れるということに意味があるのか・・・そんなことを決めなくてはいけないのか・・・
もう駄目なら、自然に別れが訪れる筈だ・・・。
Hはおれに反してはっきりとした声で言った。
だが、何故それを顔を背けて言う必要があるのだろうか。
お前が分からない。
おれはHを見つめ続けた。
Hのその顔に答えがあるような気がして。
おれはいつからこんなに弱くなったのだろう。
Hに、この最後の瞬間まで答えを求め続けるなんて、おれはそんな人間だったろうか。
おれはHが見えないのじゃなく、自分が見えないだけなのか?
おれは何故・・・自分を見失ったのだ・・・
・・・Hが顔を背けているのを見つめる内におれは悟った。
直感した。
Hがおれを見てないからおれは自分を見失ったのだ。
おれはHの目であったのだ。Hがおれを見る、その目がまさしくおれであったのだ。
そして今Hはおれを見ていない、確かに見ていないから、おれも、おれ自身が見えない。
そんなことって・・・そんなことって・・・いや、多分、事実なのだろう。
おれは消えた。
もう存在していない。
顔を作る必要なんてないし、言葉を選ぶ必要もない。
おれにはもう顔はなく、そして言葉もない。
あってなきが如くに。
は、は、は!
おれは笑った。
不思議とHにはそれが聞こえたらしくこちらを見た。
だがおれにはやっぱりおれ自身が見えなかったから、やつはおれを見た訳ではなかったのだ。
Hは薄気味悪そうな顔をしていた。
その顔が朧気な月光に照らし出されて不気味に見えた。
おれたちはお互いに気色悪そうな顔をしていた。
おれは笑ったのか泣いたのか分からないが、おそらくそのどっちともを実行したのだろう。
は、は、は!
乾いた笑いが空気に木霊していた。
Hは気味の悪そうな表情を次第に軽蔑とすり替えて、最後にはどういう訳か薄笑いを浮かべておれを見ていた。
おかしなものでも見るような目をしておれを見つめていた。
口元は冷たく歪んで、彼独特の笑みを洩らしながら。
終わりだ・・・おれたちは遠くへ来すぎたようだ・・・お互いに望まない方向へ来てしまった・・・
おれは笑ってはいなかった。だが正確にはどうか分からない。
破局というものはこんな風にして訪れるものだと感じた。
破局というものは、こんな薄闇に月明かりを落としただけの冷たい空気の中で、
薄笑いを浮かべた仮面をかぶったような男の口から言われるものなのだ。
おれはまたおかしくなって笑い出しそうになった。
H、H、H、H!
お前はもうおれにとって虫けら同然の人間でしかないのか!
おれの足の下で惨めに踏み潰されるあの、無数の蠢く低俗な虫けら!
お前はそんなものに成り下がってしまったのか!
ひ、ひ、ひ!
お前は何て馬鹿なんだ・・・そしておれはもっと救いようがない。
お前を・・・虫けらのお前を踏み潰せないのだから。
その黒々と光る醜い体を冷たいアスファルトに押しつけて、擦り付けて、微塵も残らないくらいに始末することがおれには出来ないのだから!
お前の首をへし折る力がおれにはないようだ。
お前の顔に唾を吐きかけて、お前の困惑する顔を悠然と見返しせせら笑って、
お前の泣き出そうと歪む唇を最高の蔑みを持って眺める力が、
おれにはもう・・・いつからか・・・ずっとないのだから・・・
代わりにお前がおれを踏み潰せばいい。
今のようにおれを見て薄笑いを浮かべ、更におれの惨めな姿を見て、腹を抱えて笑えばいい。
おれの眼前に指を突き出して、おれを見ては笑い、笑ってはおれを見て、立つことしか知らずにいるおれを、
死にそうになるまで笑ってしまえばいい!
H、今のお前にはそれが出来るだろう。
何故やらないのだ?
おれはもうお前を殺せない。
お前を笑えない。
以前おれを笑わせた全てが今のお前にはない・・・いや、笑っていたおれはもうここにはいない・・・
お前を殺すことの出来るおれ、そしてお前が愛していたおれという人間は、ここにはいない・・・なんてことだ・・・
H・・・H・・・H・・・お前を呼ぶことが出来ない・・・。
おれはどうかしている。
自分が分からない。
自分が何を畏れているのか。
おれはお前に、縋り付きたいんだ・・・いや、そうじゃない・・・お前を破滅させたいんだ・・・
いや・・・これも違う・・・おれは・・・おれは・・・自分の破滅を望んでいたのか?
自分が滅ぶことを望んでいたのか?
そして今おれは粉々に砕け、お前は満足そうに笑っている。
お前はこれを隠していたのだ・・・
おれを破滅させることが出来るということを隠していたのだ・・・
そうか・・・おれは破滅した・・・満足だろう?
笑え、笑えよ・・・
おれが言うまでもなく、Hはもう遠慮もせずに口を歪めて肩を震わせて、くつくつと笑っていた。
おれの顔を見て、さも愉快そうに笑っている。
Hはこれをしたかったに違いない。
おれが居竦んで動けずにいるさまを見て、肩で笑いたかったに違いない。
おれはきっとどんなにか惨めな顔をしているだろう・・痛快だろう・・・
そんな顔をするとは意外だったよ。おれはてっきりお前の方から言い出すのかと思っていた。
お前は言わなかった・・・言うまでもなく思っていたのかもな。
Hは依然笑いつつそんなことを言って、そろそろ間が悪くなってきたのか笑いを堪えようとしていたが、
おれの顔を見て、とうとう我慢出来ずに顔を背けて背中を震わせて笑っていた。
おれは完全に硬直したようになっていた。
Hの笑い声がおれを雁字搦めにし、身動きがままならない。
だが、これでいいのだ。
やつには笑わせておけ。
おれは痛くも痒くもない・・・ただ・・・ただ・・・いや、どうだっていい。
こんな終幕が用意されていたとは。
そしておれは最後にHに追い抜かれ、Hは赤い舌をぺろりと出して去って行くのだ。
おれはいつまでも、いつまでも、ここに立っているだろう。
そして自分が結局、Hをどう思っていたかなど分からないのだろう。
考えもしなかった・・・。
Hは不意にまた元の冷たい顔つきに戻った。
おれはもうどうなっても構わなかった。
Hはおれにとって虫けらの神様のようなものだ。
そう・・・虫けらの神様のような・・・
しかしそれももうすぐおれとは関係のない世界へ足を踏み入れてしまうだろう。
おれは今そこにいるHよりも、おれの心の中にいる、おれの妄想が生み出すHを強く感じている。
Hが消えても、妄想は膨らみおれの中であいつは永遠に息づく。
だからここにいるHなんて、いないも同然だというのに・・・
Hは何か呟いて、そして背を向けて去って行った。
何と言ったかは聞き取れなかった。
だがおそらく、さよならと言ったのだろう。そういう意味の言葉を言ったのだろう。
つまり、さようならとか、じゃあなとか、死んでしまえとか、くそったれとか、そういう意味の言葉を。
愛している。おれは。
Hを愛している。
いつもそれだけを感じていた。そしてそれで十分だった。
愛していただけで、それで良かった。
おれはHを愛していないというのか?
そんなことはない、いつだっておれはあいつを・・・愛する・・・
おれたちが過ごした時間・・・過ごした日々・・・おれがあいつを愛していない訳がない。
こんなに醜く歪んだ愛情であっても、あいつはそれを感じて一時はそれを至福とまでに思った筈だ。
おれがどんなに間違った情熱をやつに傾けていようと、それがやつを幸せにしなかったと何故言える?
おれは・・・確かにHを屈折した思いで見ていたが、それが何だというのだ。
これを愛情や情熱や憎悪や軽蔑や、
そして汚辱、侮蔑、恥辱、愚弄、蔑み、暴力、苦痛といわないで何と言おう?
やつの身体に両手を突っ込んで、脈打つ心臓をぎゅうきゅう締め付け、むしり取って、返り血を浴びて、
そしてやつは笑い、おれも笑い、おれたちは鮮血にまみれ、互いに取り出した臓器を見つめて、
ただ笑い、笑い、笑うだけ。
それが愛と言わずに何と言うのだ?
おれはHを愛す。
Hの風に揺れる黒い髪を、時々死んだように表情をなくす両の瞳を、冷たく引きって笑うその唇を、
青白くどんよりとしたその顔全て、普段は邪魔そうにしているがいざとなると思わぬ力を漲らせる腕、
大きくがっしりとしているのに繊細な動きをする手、指先、機械的に交互に出される足、足音、
お前の好きなもの、
好きな人間、
好きな色、
好きな季節、
好きな言葉、
そしてその全てに反対な嫌いなもの、
お前が吸う空気、
お前が吐く息、
お前が俯く時、
お前が眠る時、
お前が笑う時、
お前が無表情で無感動になる時、
お前が幸せを感じる時、
お前が苦痛を堪える時、
お前が誰かを殴る時、
お前が淫らな妄想に沈む時、
お前がおれを愛した時、
お前がおれを忘れた時、
お前が・・・お前が・・・・・・・・
好きだ。
最後の言葉がおれの口をついてほとばしり、闇の中に木霊した。
だが、もうそこにはHはいず、おれもそれを知っていて叫んだのかも知れなかった。
闇がおれの言葉をひっそりと呑み込んでしまうのを感じていた。
そう、結局やつはおれの気持ちを知らない。
最初から最後までどう思っていたかなど、知らないのだった。
あいつの身体を両の腕にしっかりと抱き締め、百の口づけをしてやりたいほどに求め、
あいつの生きているところ全てを粉々に切り刻んで滴る血液を喉を鳴らして飲み干してしまいたいほどに、
愛していたことなど、
Hは知らない・・・知らずに去って行く。
おれは人知れず笑っていた。
最初は自分でも気付かないほどの微かな笑い。
そしてそれはその内森閑とした通りに響きわたるくらいの大きな笑い声と化した。
ひ、ひ、ひ、ひ!
なんて笑えるのだろう。なんて愉快だろう。こんなに腹の底から笑えることもそうないだろう。
おれは笑い続けた。
笑うのを止めようと思ったがまるで出来なかった。
笑うことに疲れ、怯えさえ感じて、もうよそうと思うのに、おれはいつまでも闇に反響する笑い声を聞いていなければならなかった。
ひ、ひ、ひ、ひ!
おれは段々と苦痛になってきた。
もう笑いたくはない。やめてくれ・・・笑うのはいやだ・・・だが、おれは笑う。
いつまでも笑う。
笑う理由など見つからない・・・それなのに・・・
おれは大層長い間そうやって誰かに笑わせられていた。
いつしかそれが、
涙と嗚咽に変わったのをおれすらも気付かずに、
闇に向かって、
か細く、
途切れ途切れに、
ヒ、ヒ、ヒ、ヒ、ヒ・・・と。
THE END
|| 後書き ||
|| 伽藍堂 || 煩悩坩堝 ||